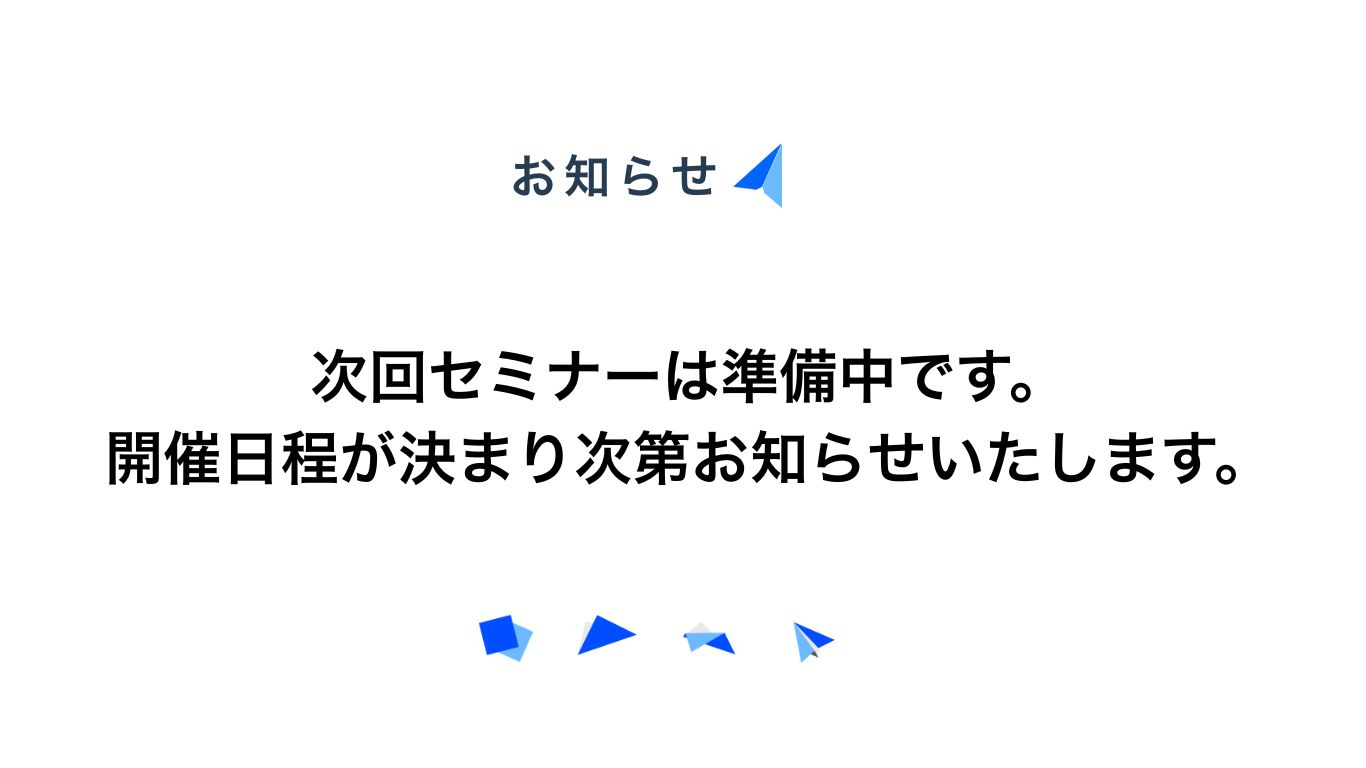2025年の沸騰ワードを番付にしたら、おそらく「関税」は外せないと思います。1月に米国でトランプ政権が誕生し、少し経った3月終盤ごろから世の中を動揺させたことは記憶に新しいでしょう。
関税と聞くと何だかよくないイメージですが、そもそも関税とは何なのかざっくりとした認識にとどまっている人も少なくないと思います。仕組みを知っておくと今後のニュースの理解度も高まっていくはずなので、今回は関税について分かりやすさを軸に簡単解説をします。
関税とは?
関税とは、外国から入ってくる品物にかけられる「税金(お金)」のことです。例えば、日本にアメリカのオレンジが入ってくるとき、そのオレンジに税金がかかります。この税金を払うのは、オレンジを輸入する会社です。ここが勘違いされやすいところで、日本が支払う税金が増えるわけではありません。
この仕組みは、国が自分たちの産業(工場や農業など)を守るために使われます。たとえば、外国から安い品物がたくさん入ってくると、日本で作っている同じような商品が売れなくなってしまいます。その際、関税をかけることで外国の品物を少し高くして、日本のものを買いやすくしようとする政策です。

流れとしては、関税引き上げ→輸入する会社が支払う税金増加→増税された分を販売価格に上乗せする→消費者の負担が増える…このようなイメージです。輸入品の価格が高くなれば、相対的に割安感が出てくる国内品の需要が増えるという仕組みですね。
関税のメリット・デメリット
自国の産業を守るための政策ではありますが、もちろん良い面と悪い面が存在します。
メリット
(1)自国の産業を守れる
関税によって外国商品の割安感が薄れるため、国内で生産している会社や農家が生き延びやすくなる。
(2)税金として国にお金が入る
関税は税収となるため、自国の公共政策や新たな成長戦略などに使える資金が増える。
(3)戦略的に使える
関税は外交の道具としても使うことができる。
デメリット
(1)商品が高くなる
関税をかけると輸入された商品が高くなり、消費者が買うときの負担が増える。
(2)他の国とのトラブルになりうる
ある国が関税を上げると相手の国も「うちも上げる!」と対抗してくることがある。そうなると貿易がうまくいかなくなり、結果的に両方の国にとって損になる可能性がある。
(3)国際関係が悪化することがある
関税は時には「けんかのきっかけ」になることもあり、こちらは後述します。
外交でどのような手段として使われるか
関税は不公平を解消するためのただの税金ではなく、外交という国と国の関係を動かす手段にも使われます。特に注目されたのが、アメリカの第1次トランプ政権(2017年~)が行った関税政策です。
<トランプ大統領と中国の関税戦争>
2018年にトランプ大統領は、中国から多くの商品が安く入ってきて、アメリカの産業が打撃を受けていると考えました。そこで、トランプ大統領は中国からの輸入品に高い関税をかけました。
対象となったのは、例えば鉄やアルミ、電気製品、衣類などです。すると中国も反発して、アメリカの商品に対して関税をかけ返しました。こうして「関税のやり合い」が始まり、世界中に影響が広がりました。当時は「米中貿易戦争」という言葉がよく使われました。

このように、関税は「相手国にプレッシャーをかける道具」としても使われます。ただし、お互いに関税を上げ合うと、どちらの国の企業や消費者にも負担がかかってしまいます。
<昔の日本も関税で悩んでいた?>
日本も昔、関税で苦労していました。明治時代のはじめ、日本は外国と不平等な条約を結ばされていたことがあります。代表的な条約は1858年の日米修好通商条約をはじめとする安政五カ国条約(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、オランダとの条約)です。
その中には関税自主権(自分で関税のルールを決める力)がない」という問題があり、税率は外国と協議して決める必要がありました。要は、日本は外国から品物が入ってきても自分たちで関税の金額を決められない状況です。
関税は諸刃の剣
関税は国を守る手段となる一方で、外交で相手にプレッシャーをかけることにも用いられます。
ただ、関税をめぐって争いが起きると世界の経済や私たちの生活にも大きな影響が出るため、簡単に扱えるものではありません。貿易相手国との関係性が悪化するだけでなく、最悪の場合は自国だけ仲間外れにされるリスクもあるため、メリット以上のデメリットとなることも十分に理解しておく必要があります。
2025年1月に誕生した第2次トランプ政権下においても、相互関税が大きな話題となっています。トランプ大統領もむやみやたらに関税をかけるというわけではなく、最初に強硬姿勢を提示し、その後の協議で落としどころを探っていくスタイルです。世間ではトランプディールともいわれていますね。
トランプ大統領としてはこの辺りが妥協点だろうと思っていても、他国からするとそれは譲れないということもあります。交渉が長引くにつれて国家間の関係性、経済ともに悪化しかねないため、迅速に交渉をまとめることが重要です。各国の交渉がどのように進んでいくのか気にしながらニュースを見ていくと、投資においても何か思いつくかもしれませんね。
【免責事項・注意事項】
本コラムは個人的見解であり、あくまで情報提供を目的としたものです。いかなる商品についても売買の勧誘・推奨を目的としたものではありません。また、コラム中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。
※本記事は2025年7月4日に「いまから投資」に掲載された記事を、許可を得て転載しています。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!