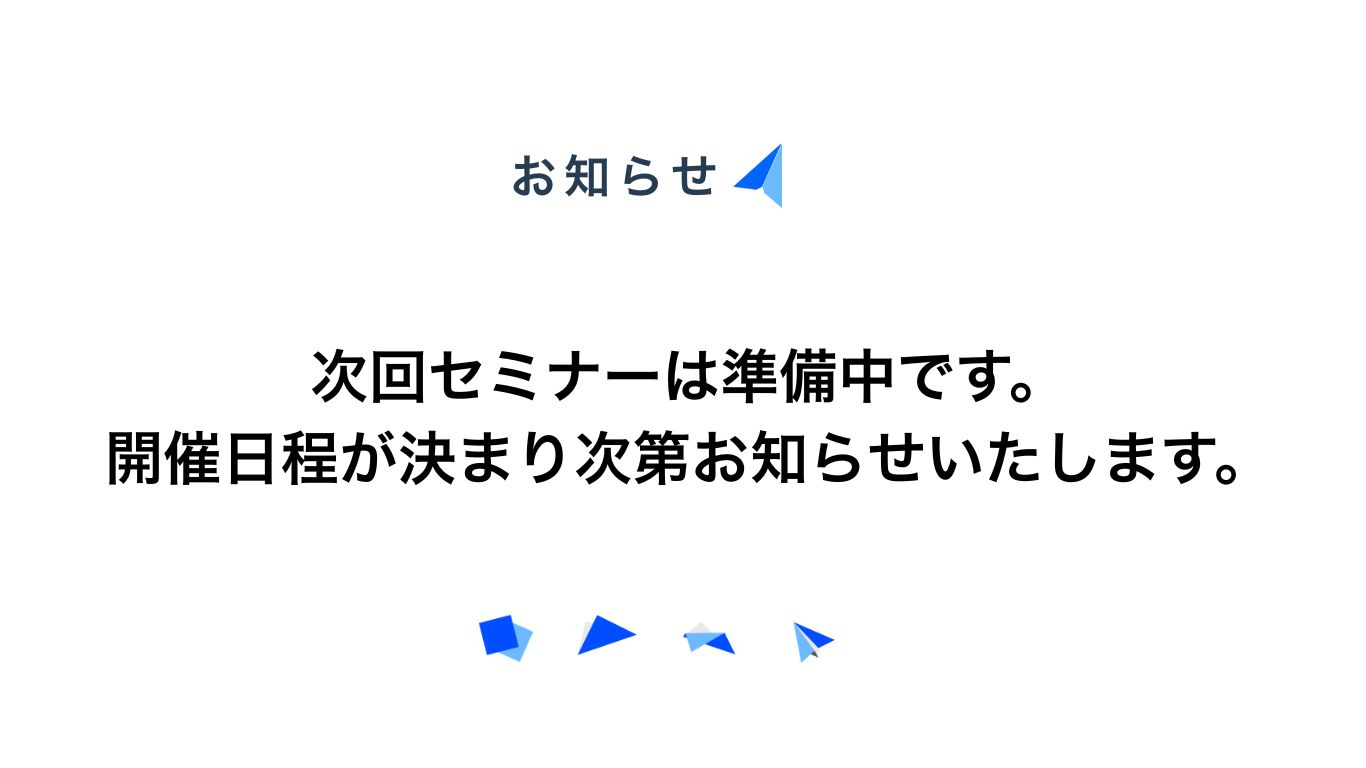―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は4月28日週に3.96円と、その前の週の4.14円から縮小した。週足では、続伸。前週比では1.28円の上昇となった。年初来リターンは7.8%安へ縮小した。日米協議が終了し、三村財務官が引き続き、米国から為替水準に言及はなかったと説明するなか、ドル円は買い優勢。日銀金融政策決定会合後は、展望レポートと植田総裁会見内容がハト派的で、145円台へ戻した。中国が米国との協議に前向きな姿勢を示唆すると、一時145.93円と約2週間ぶりの水準を回復した。
- 日銀金融政策決定会合では、①展望レポートで25年度と26年度の成長と物価(コア)見通しを引き下げ、植田総裁も27年度の見通し追加に合わせ「物価安定の目標と概ね整合的な水準で推移すると考えられる時期は、見通し期間の後半になる見込み」と言及。従来の物価2%達成時期を1年後ろ倒しさせた。また、「物価上昇が伸び悩む中で無理に利上げをすることは考えていない」とも言及。年内利上げ観測を後退させる内容となった。もっとも、年内利上げなしとの判断は早計だろう。トランプ関税の混乱は収束に向かいつつあり、米株相場も4月の下落を概ね打ち消しとなった。Fedが利下げに急がない立場を維持し、ドル高・円安リスクが意識される事態になれば、日銀が再びタカ派に転じかねない。2回目の日米協議に三村財務官が出席していることもあり、為替に絡み、日銀の金融政策正常化が非公式で議論される余地も残す。
- 5月5日を中心に台湾ドルや香港ドルなど、アジア通貨が対ドルで急伸したことも、留意しておきたい。台湾中央銀行は5月5日に一時5%高と、取引時間中としては約30年間で最大の上げを記録した動きを受け、声明で「マールアラーゴ合意」のような、ドル高・台湾ドル是正によるものではないと説明。同時に、「憶測的なコメント」を控えるよう要請した。もっとも、まもなく半期に一度の為替報告書の公表が予想されるだけに、トランプ政権が同報告書を通商協議のレバレッジに使うリスクも視野に入る。従って、対円を含め、アジア通貨でのドル高は長続きしないと考えられる。
- 5月FOMCは、前回に続き無風となりそうだ。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、トランプ関税を受け、利下げに急がない姿勢を崩していない。何より、足元の米経済指標は底堅さを示す。米Q1実質GDP成長率・速報値は3年ぶりマイナスも、輸入の急増が主因。GDP構成項目で変動の大きい政府支出や在庫、貿易統計の影響を除外し、個人消費と企業支出の総額を表し国内の需要を表す民間最終消費は同3.0%と堅調だった。米4月雇用統計も、非農業部門就労者数(NFP)が前月比17.7万人増と底堅く、労働参加率が上昇も失業率は前月と変わらなかった。また、ベージュブック(地区連銀報告)では、トランプ関税を受け「関税」や「不確実性」の文言の登場回数が急増し、インフレ再燃の懸念を映し出す一方で、「景気後退」の文言はゼロと、憂慮されている様子はない。従って、5月FOMCで利下げの地ならしを行うとは想定しづらい。
- 5月5日週に発表となる主な経済指標は、5日の米4月ISM非製造業景況指数、6日に中国4月財新サービス業PMI、8日に米新規失業保険申請件数と米Q1単位労働コスト・速報値、9日は中国4月貿易収支、日本3月実質消費支出と実質賃金など。
- その他、7日は米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策発表とパウエルFRB議長の会見、8日は日銀金融政策決定会合の議事要旨、イングランド銀行の政策発表を予定する。9日はイングランド銀行のベイリー総裁の発言を始め、バーFRB理事、NY連銀総裁、クーグラーFRB理事、リッチモンド連銀総裁、クックFRB理事の発言に加え、ウォラーFRB理事とNY連銀総裁の討論、ボウマンFRB理事とセントルイス連銀総裁、クリーブランド連銀総裁の討論が控える。
- ドル円のテクニカルは、弱い地合いが一段と後退。一目均衡表では引き続き三役逆転を形成し、21日線を始め移動平均線は全て下向きだが、一目均衡表の転換線に加え、21日移動平均線もサポートに転じつつある。その反面、一目均衡表の基準線は、ローソク足の上ヒゲが週後半に2日連続で上抜けたが、実体部では超えられず。2025年に入ってから、戻り局面で一目均衡表の雲を突破できていないところ、これらが下向きとなっているのも、気掛かりだ。2025年からの戻り局面で、RSIが割安感と割高感の中間にあたる50を超えてくると買い戻しが一服してきたことも、意識しておきたい。
- 以上を踏まえ、今週の上値は一目均衡表の基準線が近い145.20円、下値は心理的節目と4月22日の安値付近の141.50円と見込む。
1.先週のドル円振り返り=日銀会合後のハト派的な植田総裁発言で、約2週間ぶりの146円に接近
【4月28日~5月2日のドル円レンジ: 141.97~145.93円】
ドル円の変動幅は4月28日週に3.96円と、その前の週の4.14円から縮小した。週足では、続伸。前週比では1.28円の上昇となった。年初来リターンは7.8%安へ縮小した。日米協議が終了し、三村財務官が引き続き、米国から為替水準に言及はなかったと説明するなか、ドル円は買い優勢。日銀金融政策決定会合後は、展望レポートと植田総裁会見内容がハト派的で、145円台へ戻した。中国が米国との協議に前向きな姿勢を示唆すると、一時145.93円と約2週間ぶりの水準を回復した。
28日、ドル円は買い先行後に失速。ドル円は東京時間、三村財務官が前週末の加藤財務相に続き、ベッセント財務長官がドル安・円高を望むとの報道について「100%事実でない」と発言したため、買いが先行し144円乗せを伺う展開を迎えた。もっとも、ロンドン時間から売りに転じ、一時は142円割れを迎えた。
29日、ドル円は小動き。東京市場が昭和の日を受け休場のところ、ロンドン時間でドル円が買い戻されつつも一時142.76円まで本日高値を更新するにとどまった。
30日、ドル円はもみ合いを経て上昇。東京時間は142円台で軟調だったが、ロンドン時間から買いが入り、一時143.19円まで本日高値を更新。NY時間では米4月ADP全国雇用者数が市場予想以下だったほか、米Q1実質GDP成長率・速報値が市場予想のプラスに反し3年ぶりのマイナス成長となりつつ、142円後半を中心にもみ合いが続いた。
5月1日、ドル円は大幅高。日銀金融政策決定会合で市場予想通り政策金利据え置きとなったほか、展望レポートで成長と物価見通しが引き下げられ、利上げ期待が後退するにつれ、ドル円は買いが優勢となり144円を超えていった。植田総裁が会合後の会見で物価見通し2%達成の時期の後ずれについて発言すると、144.70円台へ上昇。ロンドン時間では伸び悩んだが、NY時間にかけ米4月チャレンジャー人員削減予定数が前月以下にとどまると、日米金利差縮小期待が低下し145円台を超え、一時145.74円まで切り上げた。
2日、ドル円は買い先行後に伸び悩み。ドル円は前日の流れを引き継ぎ買い優勢だった上、中国商務省が米国との通商協議の可能性を現在検討中との報道官談話を発表したことも、上値を押し上げ一時145.93円と4月10日以来、約2週間ぶりの高値を付けた。もっとも、ロンドン時間には米4月雇用統計を控え上げ幅を縮小。NY時間では米4月雇用統計の結果が堅調でも一時は144円を割り込み、植田総裁会見後の上げ幅を打ち消す動きをみせつつ、144円後半へ切り返し週を終えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!