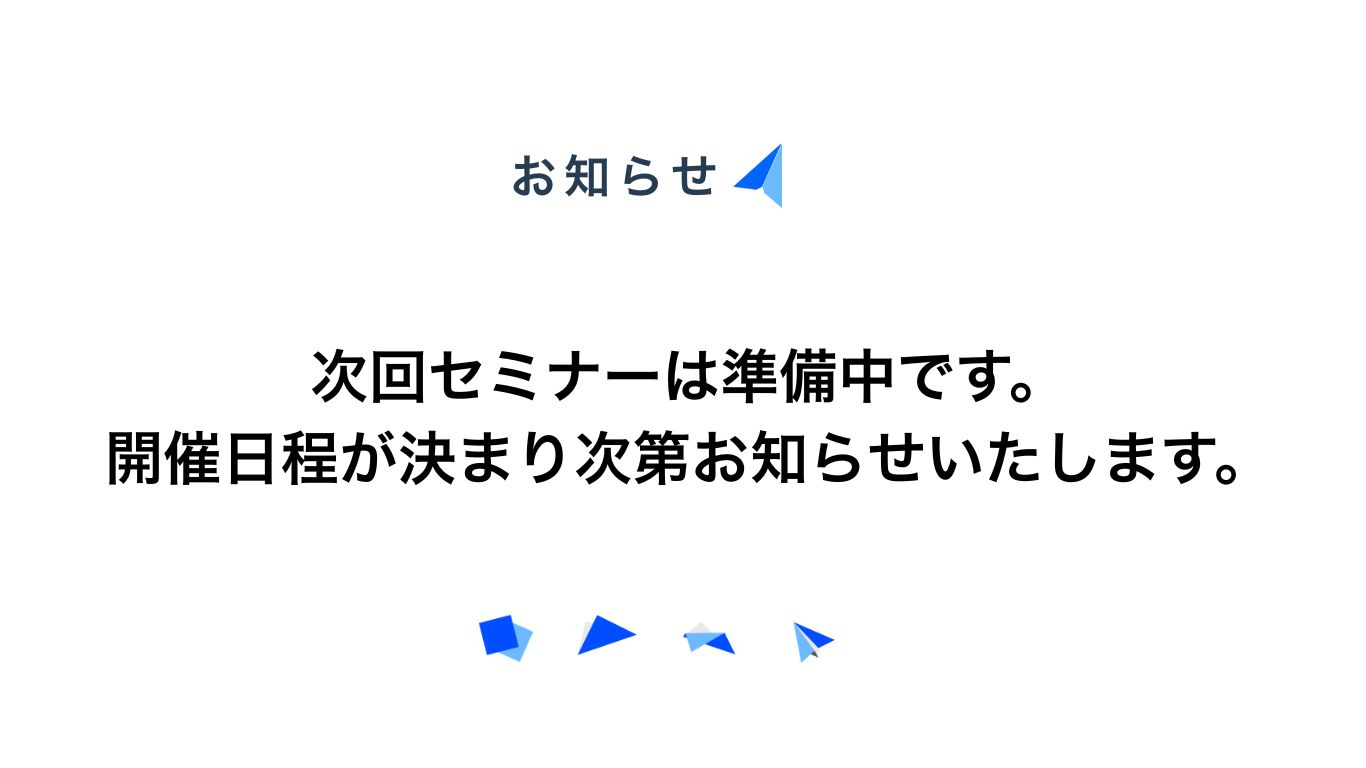EUのロシアからのエネルギー依存
ロシアがウクライナ侵攻を行ったのが2022年2月で、早くも3年半弱の月日が経ちました。
このウクライナ侵攻で欧州連合(EU)は、当然のようにウクライナサイドに立ったわけですが、欧州各国からするとこれまでロシアからエネルギーを輸入していたことで、当時はロシアにエネルギーの首根っこをつかまれている欧州各国はエネルギー危機に陥るとされていました。
EUのロシアからのパイプラインガスの輸入は、EUのホームページによりますと侵攻前の2021年の1502億立方メートル(bcm)でした。
しかし、禁輸措置などを取ったことで、2022年には782bcm、2023年には429bcmまで大幅に減少しています。
全体の比率では2022年は40%超がロシアに依存していたものが、2023年には約8%まで大幅に縮小したことになります。
ロシアの代わりにEUが輸入を依存したのが、ノルウェーと米国で、両国の依存比率は急速に上昇しました。
その他の供給国としては、北アフリカ諸国、英国、カタールなどもあります。
地政学上はロシアからの方がコストは割安なのでしょうが、禁輸措置を取っていることでこのように輸入依存度に変化が生じるのは当然ですが、EUからすると代替でもエネルギーを獲得できたことは様々な面で助かったことでしょう。
ロシアも禁輸措置で困らず?
一方のロシアはどうでしょうか?
EUというお得意先が禁輸措置をしたことで、売れるモノが売れなくなったことで経済にダメージを受けると思われていました。
エネルギーとクリーンエアの研究センターであるCREAによると、2023年7月ことにはウクライナ侵攻時から比較すると総輸出量の半分程度まで減少しました。
しかしながら、徐々に底を打ち、やや戻している傾向になります。
パイプラインガスに関してはEUへの輸出が大幅減少になったことで、伸びが悪いままです。
ただし、石炭・原油・LNG・海上石油製品 ほかのエネルギーの輸出はそれほど大きく減少しています。
それらのエネルギーの主な輸出国は、LNGは依然としてEUが首位なものの、石炭は中国がロシアの石炭輸出全体の45%を購入し、インド(18%)がそれに続いています。
トルコ(10%)、韓国(10%)、台湾(5%)がトップ5となっています。
原油は中国がロシアの原油輸出の47%を購入しており、インド(37%)、EU(7%)、トルコ(6%)がそれに続いています。
LNGは上記のようにEUが首位でロシアのLNG輸出量の50%を購入しており、最大の購入国となっている。次いで中国(20%)、日本(18%)となっています。
石油製品の最大の購入国であるトルコは、ロシアの石油製品輸出の24%を購入しており、中国(12%)、ブラジル(11%)がそれに続いているという状況です。
禁輸措置の効果はあるものの、多岐にわたって輸出先があることで、想定よりもなんとか持ちこたえる展開になっています。

トランプ関税もそのうち
米国は予定通りに、例外なく鉄鋼・アルミ関税を発動しました。
このことにより米国へ鉄鋼・アルミを輸出していた国々は大きな影響を受けることでしょう。
ただし、上述のように世界の流れは代替先(国)を探していくことが多々あります。
そして、代替先が見つかった時には、一番影響を受けるのは関税をかけていた国、すなわち米国になる可能性もあります。
その時にドルはどのようになっているのか、ということを考えながら取引をする必要がありそうです。
【免責事項・注意事項】
本コラムは個人的見解であり、あくまで情報提供を目的としたものです。いかなる商品についても売買の勧誘・推奨を目的としたものではありません。また、コラム中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。
※本記事は2025年6月23日に「いまから投資」に掲載された記事を、許可を得て転載しています。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!