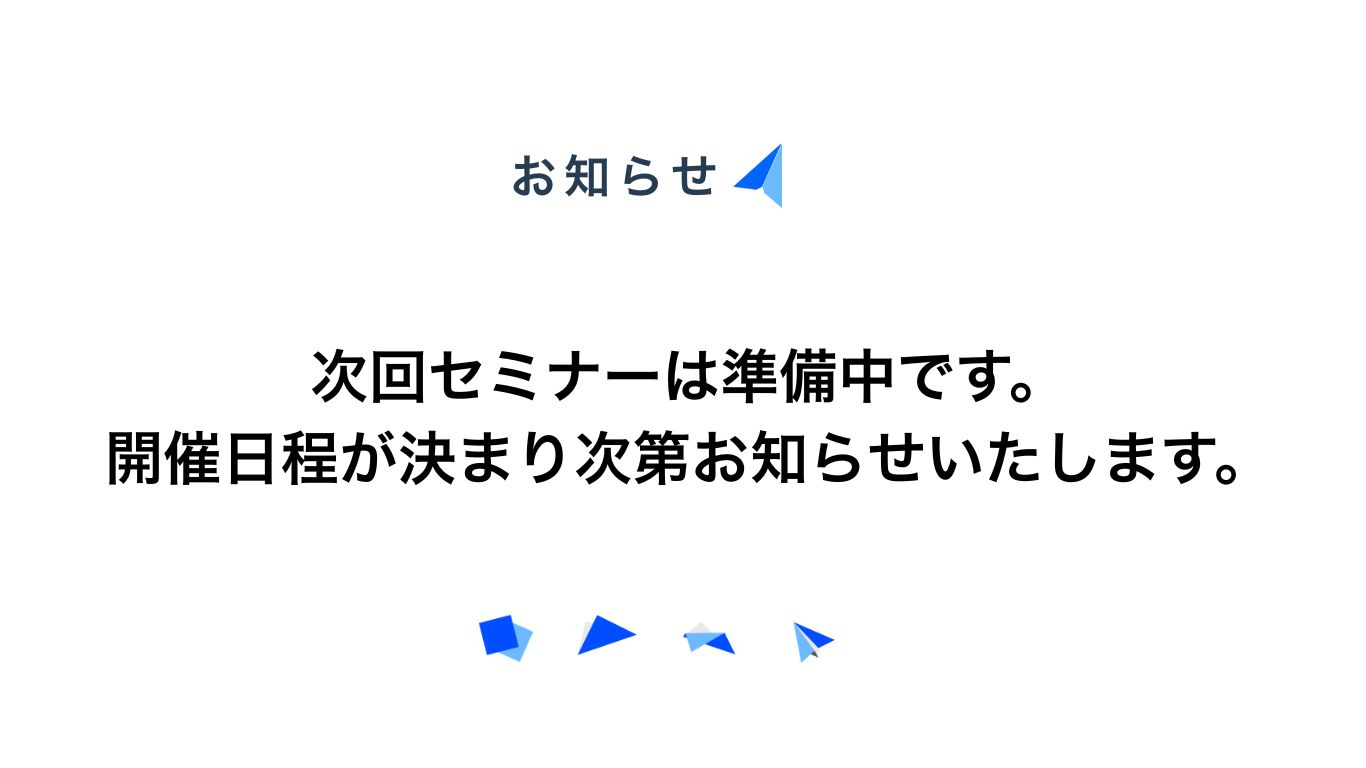―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は9月29日に週に2.95円、9月22日週に2.50円から拡大した。9月29日週までの週足では、6週ぶりに反落。前週比では2.03円の下落となり、年初来リターンは前週の4.9%安から6.2%安へ戻した。9月22日週は、パウエルFRB議長が10月利下げ示唆せず、米Q2実質GDP成長率・確報値や米新規失業保険申請件数が強い結果となったため利下げ期待が後退し、一時149.96円と8月1日以来の150円乗せが迫った。一転して9月29日週は、ハト派とされる野口審議委員が予想外に年内利上げに前向きと受け止められる発言を受けてドル円は急落。米政府機関の閉鎖も重なり、一時146.59円まで売られた。もっとも、植田総裁の発言が10月利下げに前向きと解釈されず、自民党総裁選を週末に控え、週後半は147円台を中心としたレンジに戻した。
- 高市早苗氏が自民党総裁に就任してから、ドル円は8月4日以降続いた145~148円をコアとしたレンジをブレークした。高市氏が「責任ある積極財政」を掲げるため、財政拡張が懸念されるほか、日銀の利上げ観測後退(特に10月会合での観測)――が挙げられる。高市氏が首相指名で選出されるかは不透明だが、純政府債務が2008年Q3以来の水準まで改善するなか、成長重視の財政出動を行うシナリオが想定される。日銀については、本田元内閣官房参与や若田部元日銀副捜査など高市氏の経済ブレーンが指摘するように、利上げに慎重となりうる。その場合、円一段安が視野に入り、トランプ政権の横槍が意識される。ただ、高市新政権が防衛費GDP3.5%で「ディール」を模索するなら、交渉の余地が生まれるシナリオにも留意すべきだろう。日米首脳会談で、トランプ政権の円安へ向けた姿勢を含め、確認することとなりそうだ。
- 米中間で再び緊張が走り、中国がレアアースの輸出規制強化を発表した翌日、トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルにて11月1日から対中追加関税を100%へ引き上げると投稿。中国商務省はこれを受け、レアアースは民間用途で申請すれば許可を付与すると説明したほか、「対話を通じて懸念を解決」する意思を示した。ベッセント財務長官は10月13日、米中首脳会談は予定通り行わる見通しに言及しており、一段の対立激化は避けられるのではないか。
- 10月13日週の主な経済指標として、15日に中国9月消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)、16日に日本8月機械受注、豪9月失業率、米10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、17日にユーロ圏消費者物価指数・改定値、米9月鉱工業生産などを予定する。同週に発表予定だった米9月CPIは10月24日に発表が後ろ倒しされるなか、その他の米政府発表の重要指標(指標予定の緑文字)も、仮に政府機関の閉鎖が解除されても、遅れる公算が大きい。
- その他、政府・中銀関連では、13日にIMF世銀年次総会、14日にパウエルFRB議長を始めボウマンFRB副議長、ウォラーFRB理事、ボストン連銀総裁、ベイリー英中銀総裁の発言を予定する。15日に日本20年利付国債入札、ミランFRB理事やウォラーFRB委理事の発言や米地区連銀報告(ベージュブックの公表)に加え、G20財務相中央銀行総裁会議が行われ、植田総裁の発言飛び出す場合も。16日は田村審議員の発言、米国からはボウマンFRB副議長やバーFRB理事、ミランFRB理事、ウォラーFRB理事、そしてラガルドECB総裁の発言が控える。17日は内田副総裁を予定する。
- ドル円のテクニカルは、非常に強い地合いを維持。一目均衡表は三役好転が成立し、10月10日に2024年9月安値と2025年1月の高値の38.2%押しにある151.51円を抜けたが、週明けには同水準を上回って推移を続けている。一方で、中国のレアアース輸出規制強化をめぐる緊張関係の着地点が現時点で不透明で、ドル円が一気に155円を抜けて上滑りするかは微妙な情勢。RSI(14日)は10月9日に72.02と、明確に2024年7月2日以来となる割高の節目70超えに至ったが、その後は63台へ押し返された。ドル円の上昇の勢いは、割高感の節目70超えが度々確認された2022年~24年当時ほど強いのか、不透明感が残る。
- 以上を踏まえ、今週の上値の目途は2024年9月高値と25年1月高値を結んで引いたトレンドラインと心理的節目が控える154.50円、下値は心理的節目の150円ちょうどと見込む。
1.ドル円振り返り=高市自民党新総裁でドル円は2円窓開け、2月中旬以来の153円乗せもトランプ砲で上げ幅を縮小
【10月6日~10日のドル円レンジ:149.05~153.28円】
ドル円の変動幅は10月6日週に4.23円、その前の週の2.95円から拡大し、6月23日週以来の大きさとなった。週足では、6週ぶりに大幅反発。前週比では3.68円の上昇となり、年初来リターンは前週の6.2%安から3.9%安へ下げ幅を縮小した。10月6日週は、自民党の高市新総裁就任を受けて、財政拡張・日銀利上げ後退との見方が優勢となり、記録的な上昇を遂げた。日本8月実質賃金が8カ月連続でマイナスとなったことも、売り材料に。高市氏がドル円の一段高をけん制するような見解を表明したなかで影響は一時的で、一時153.28円と2月中旬以来の高値を付けた。しかし、トランプ大統領が中国のレアアース輸出規制強化を受けて、対中追加関税を11月1日から100%引き上げるとの発言で急落。152円を割り込んで週を終えた。
6日のドル円は急騰。自民党総裁選の結果、高市早苗氏が新総裁に就任した流れに反応し、ドル円は約2円も窓を開けて急伸。少なくとも2000年以降で最大の窓開けを記録し、東京時間は右肩上がりの展開を迎え、一時150.48円と8月1日以来の高値をつけた。NY時間入りには、急落。高市氏ブレーンの本田元内閣参与が10月利上げは困難としつつ、0.75%への利上げは経済状況が大きく悪化しない限り問題なし、ドル円の150円超えは「行き過ぎ」と発言したことが伝わり、一時149.70円台へ下落。もっとも、トランプ大統領やベッセント財務長官が高市新総裁選出を歓迎する投稿に反応し買い戻され、150円前半へ切り返してNY時間を終えた。
7日、ドル円は続伸。トランプ大統領が現地時間夜(東京時間の序盤)に民主党に政府機関の再開を呼びかけるなか、閉鎖終了への期待感もあって買いの流れが続いた。ロンドン時間も上値を伸ばし、NY時間に、NY連銀発表の米9月1年先インフレ期待が加速したこともあって上値を伸ばし、3月下旬以来の151円に乗せる展開。3月26日の高値や24年9月安値と25年1月高値の38.2%押しがある151.51円も抜け、152円も超えて一時152.05円まで上値を広げた。
8日、ドル円は前週2日から見て4日続伸。日本8月実質賃金が前年比で8カ月連続マイナスだった結果を受けて日銀の10月利上げ期待の後退を促し、ドル円の買いを後押しした。ロンドン時間には、2月半ば以来の大台に乗せ153円ちょうどへ上昇。その後は、臨時国会での首相指名が20日以降にずれ込む可能性が伝わったほか、9月FOMC議事要旨で多数の参加者が主に関税の影響を受けインフレ見通しに対する上方リスクの高まりを強調したとの文言を確認したものの、高止まりでの推移を続けた。
9日、ドル円は5日続伸。高市氏の経済ブレーンとされる若田部元日銀副総裁が年内利上げは困難、12月なら「相当強い理由が必要」との見解を示したが、東京時間は小動きだった。しかし、ロンドン勢が入ってくるタイミングで買いが再燃、153.20円台へ上値を拡大。NY連銀総裁が「年内の追加利下げを支持」と発言したことで152.40円台へゆるむも押し目買いの機会を与えるのみで、NY時間には高市氏が「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」との発言でも、152.10円台へ下落した後はすかさず買いが入り、また高市氏が「いい円安と悪い円安がある」との言及もあって、むしろ一時153.24円まで切り上げた。
10日、ドル円は堅調な推移を経て急落。ドル円は東京時間の序盤に一時153.28円と2月半ば以来の高値を更新したが、ロンドン時間入りに公明党が自民党との連立解消を決定し、152.30円台へゆるんだ。引き続き押し目と判断され買い戻されたが、徐々に戻りも鈍くなるなか、NY時間に急落。トランプ大統領が、中国のレアアース規制強化を受けて、APEC首脳会合での習主席との会談をキャンセルする可能性に触れた上で、対中関税の大幅引き上げに言及したため、152円を割り込んだ。一時は、151.51円と24年9月安値と25年1月高値の38.2%押しの水準に並ぶ展開。その後、152.20円台へ戻すも勢いに乏しく、引け際にはトランプ氏があらためて11月1日から対中追加関税を100%へ引き上げるとの見解を示し急落し、151.17円で安値引けした。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!