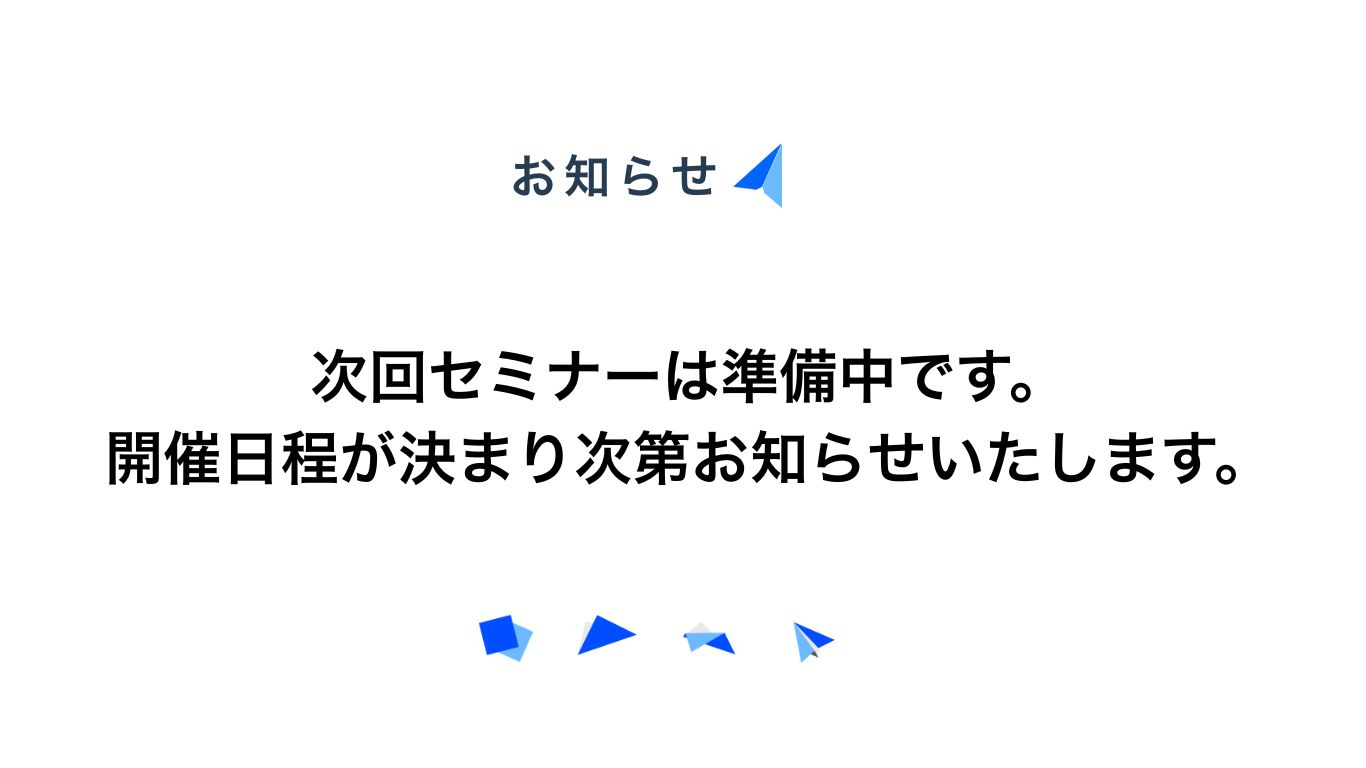―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は13日週に3.24円、その前の週の4.23円から縮小した。週足では反落。前週比では0.52円の下落となり、年初来リターンは前週の3.9%安から4.2%安へ下げ幅を拡大した。13日週は、米中貿易摩擦の激化や自民党の高市総裁の首相指名をめぐる思惑で高市トレードが一服するなど乱高下した。加えて、パウエルFRB議長が量的引き締め(QT)停止と労働市場の減速に言及。ベッセント財務長官が日米首脳会談を控え、引き続き日銀は利上げすべきとの考えを示唆し、ドル円は150円を割り込み、一時149.38円まで下落。もっとも、トランプ氏が対中追加関税100%は持続可能でないと述べたため、下げ幅を縮小し150円後半で週を終えた。
- 米中はAPEC首脳会議での米中首脳会談を前に、緊張再燃を経て、沈静化しつつある。トランプ大統領は10月10日、対中関税100%上乗せに言及、習主席との会談中止も厭わない姿勢を示したが、10月17日には対中関税100%をめぐり「持続可能ではない」と発言。習氏とは「とても良い関係にある」と述べ、公正な合意が必要との見方を強調した。ベッセント財務長官は、10月18日に中国側の交渉責任者である何副首相と夜にオンライン会談を実施し、来週にはマレーシアで米中閣僚協議を通じ、米中首脳会談の準備を進める方針と明かした。米中間の緊張再燃に使われた材料は、交渉を有利に運ぶための鞘当てに過ぎず、双方にとって急所とは言い難い。米中が本格的な貿易戦争突入への導火線になるとは想定しづらく、両国は米中閣僚協議で24%分上乗せ関税の見送りなど、妥結を見出すのではないか。
- 米企業の第3四半期決算発表が幕開けするなか、米地銀の株価が10月16日に軒並み急落。2つの米地銀による発表を受け、信用不安が発生したためだ。米銀最大手JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は10月14日、「ゴキブリを1匹見つけたら、他にもいると思うべきだ」と述べ、信用市場の構造的リスクに警鐘を鳴らす。米連邦預金保険公社(FDIC)の2025年リスクレビューは、ノンバンク金融機関(NDFI)が運用する資産の急増を指摘、総額100兆ドルを超え、米国の銀行が保有する総資産の3倍以上に達しているという。今回、問題が発覚した米地銀のうち1つは、NDFI系のサブプライム自動車ローン業者の資金繰り失敗が影響しており、米地銀の決算発表により同問題がクローズアップされれば、リスクオフを助長しうる。
- 与野党は10月17日の衆院議院運営委員会理事会で、首相指名選挙をめぐり21日実施で大筋合意した。自民党は日本維新の会は国会内の連立政権を見据えた政策協議を行い基本合意に至っており、高市氏が第104代首相に選出される道筋が固まったと言えよう。これを受けて、今週予定する日銀の政策委員は年内利上げを確保する発言が続く見通しだ。ベッセント財務長官がトーンをやわらげつつも日銀に利上げを促す発言を行っており、特に1月に利上げ示唆を行った21日の氷見野副総裁の発言が試金石となりそうだ。
- 10月20日週の中国Q3GDP、中国9月小売売上高と鉱工業生産、22日に日本9月貿易統計、英9月CPI、23日に米9月中古住宅販売件数、24日に日本9月全国CPI、米9月CPI、米9月総合PMI速報値、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値を予定する。
- その他、政府・中銀関連では、20日に中国最優遇貸出金利(プライムレート)の発表、高田日銀審議委員の発言、中国共産党第20期中央委員会第4回総会(4中総会、23日まで)21日に臨時国会召集・首相指名選挙実施、氷見野日銀副総裁の発言、APEC財務相会合(於:韓国、22日まで)、ラガルドECB総裁の発言が控える。その他、22日に米20年債入札、ラガルドECB総裁の発言、23日に日銀金融システムレポート公表、連合の春闘基本構想公表(26年春闘賃上げ目安を含む)などを予定する。
- ドル円のテクニカルは、強い地合いを維持し一目均衡表は三役好転を保つ。10月17日にローソク足は「カラカサ」で週を終え、下落反転の兆しも。21日移動平均線を下抜け、一目均衡表の基準線まで下がったものの、そこから切り返した。とはいえ、週足の終値で8月1日の高値150.92円に届かず。RSIがデッドクロスしており、MACDもデッドクロスしつつあり、テクニカル面では力強さに欠けるように見える。
- 以上を踏まえ、今週の上値の目途は前週高値付近の152.50円、下値は5月12日の高値と50日移動平均線が近い148.50円と見込む。
1.ドル円振り返り=米中貿易摩擦懸念や首相指名をめぐり乱高下、パウエル議長のQT停止やベッセント財務長官の日銀利上げをめぐる発言も影響
【10月13日~17日のドル円レンジ:149.38~152.61円】
ドル円の変動幅は13日週に3.24円、その前の週の4.23円から縮小した。週足では反落。前週比では0.52円の下落となり、年初来リターンは前週の3.9%安から4.2%安へ下げ幅を拡大した。13日週は、米中貿易摩擦の激化や自民党の高市総裁の首相指名をめぐる思惑で高市トレードが一服するなど乱高下した。加えて、パウエルFRB議長が量的引き締め(QT)停止と労働市場の減速に言及。ベッセント財務長官が日米首脳会談を控え、引き続き日銀は利上げすべきとの考えを示唆し、ドル円は150円を割り込み、一時149.38円まで下落。もっとも、トランプ氏が対中追加関税100%は持続可能でないと述べたため、下げ幅を縮小し150円後半で週を終えた。
13日のドル円は買い戻し。10月10日にトランプ大統領が対中関税100%について言及したものの、その後、トランプ氏が12日に心配する必要なしとの見解を表明したことから、買い戻しの動きとなった。自民党と連立を組む公明党の斎藤代表が連立離脱を12日に表明するも、影響は限定的。ロンドン時間に一時152.45円まで本日高値を更新。NY時間も買いの流れが続き、ベッセント財務長官が報復余地を示すなかで、中国と対話を続ける意思を表明したほか、対中追加関税100%を課す必要はないと述べ、堅調な流れを保った。
14日、ドル円は下落。序盤こそドル円は一時152.61円まで週高値をつけたが、高市首相が誕生なら、小泉防衛相・林総務相・茂木外相で調整との報道を受けて、高市トレードすなわち円売りが入るかと思いきや、逆の展開となった。中国商務省が「貿易戦争を最後まで戦う」と表明したほか、中国が米国の通商法301条調査に協力したとされる韓国造船の米子会社5社に制裁を科す方針を発表し、ドル円の下落を誘う展開。日経新聞が米国や日本の政局をめぐる不確実性を受けながらも、円安進行なら10月あるいは12月の利上げに踏み切る可能性を伝えたこともドル円の下落の一因となった。加えて、パウエルFRB議長が講演で量的引き締め(QT)の停止のほか、労働市場の減速を指摘。トランプ氏が現地時間の中国からの食用油の輸入停止に言及し、米中貿易摩擦悪化をにらみ、リスクオフの流れが加速した結果、一時151.60円まで本日安値を更新した。
15日、ドル円は続落。トランプ大統領が中国からの食用油輸入停止に言及した余波、パウエルFRB議長のQT停止発言、ゴトー日を受けて売りでスタートした。立民・維新・国民民主が午後党首会談を行うと報じられ、為替における円売りの高市トレードの巻き戻しも、下落の一因となり、ドル円は151円割れ。自民党の高市総裁が国民民主・玉木代表と会談し、首相指名へ協力を要請との報道後は買い戻され、151円後半まで下げ幅を縮小した。ベッセント財務長官が、中国が供給網を管理するなら「中国対世界」になると警告しつつ、米中対立はエスカレートせずと楽観視したため、影響は限定的。さらにベッセント財務長官が日経新聞を含めたメディア向けインタビューで「植田氏とは長い付き合い、非常に有能な人物」と評価した一方で、円相場についてブルームバーグでの8月13日付のインタビューに続き「日銀が適切に金融政策を運営し続ければ、円相場も適正な水準に落ち着くだろう」と述べ、ドル円は急落。一時150.90円まで本日安値を更新した。
16日、ドル円は3日続落。ドル円は前日のベッセント発言に加え、トランプ氏が現地時間の15日夕方に貿易戦争の状態にあるとの認識を示し、ドル円は150円半ばへ下落した。そこからは買い戻されたが、田村審議委員が引き続きタカ派的な見解を寄せるも、影響は限定的。むしろ、NY時間にザイオンズ・バンコープやウエスタン・アライアンスなど米地銀が貸倒引当や詐欺行為を受けた訴訟を発表すると、信用不安が高まり、ドル円は一時150.21円まで下げ幅を広げた。
17日、ドル円は売り先行を経て買い戻し。植田日銀総裁がG20財務相・中央銀行総裁会議で「見通しの確度が上がっていけば、その度合いに応じて適宜『金融引き締めの度合い』を調整していくという姿に全く変わりはない」と発言、日銀がその後に引き締めではなく緩和の度合いと訂正したものの、ドル円の売りを招いた。自民と維新の2回目の政策協議を受け、維新が議員定数削減を絶対条件とするなかで、自民党が反発すれば破談のリスクが見込まれ、リスクオフに拍車をかける展開。150円を割り込み、一時149.38円まで週安値をつけた。内田副総裁が米中貿易摩擦や米地銀による不確実性が高まるなかでも、従前の見方を変えなかったことも、売り要因となったもよう。ただし、自民党が議員定数削減受け入れると報じられたほか、公明、首相指名で野党党首に投票しないとの報道もあり、ドル円は再び高市トレードよろしく買い戻し。トランプ氏がFOXビジネス・ニュースのインタビューで、100%を含めた対中追加関税について「持続可能ではない」と言及したことも買い戻し材料となり、150.65円と本日高値をつけてNY引けを迎えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!