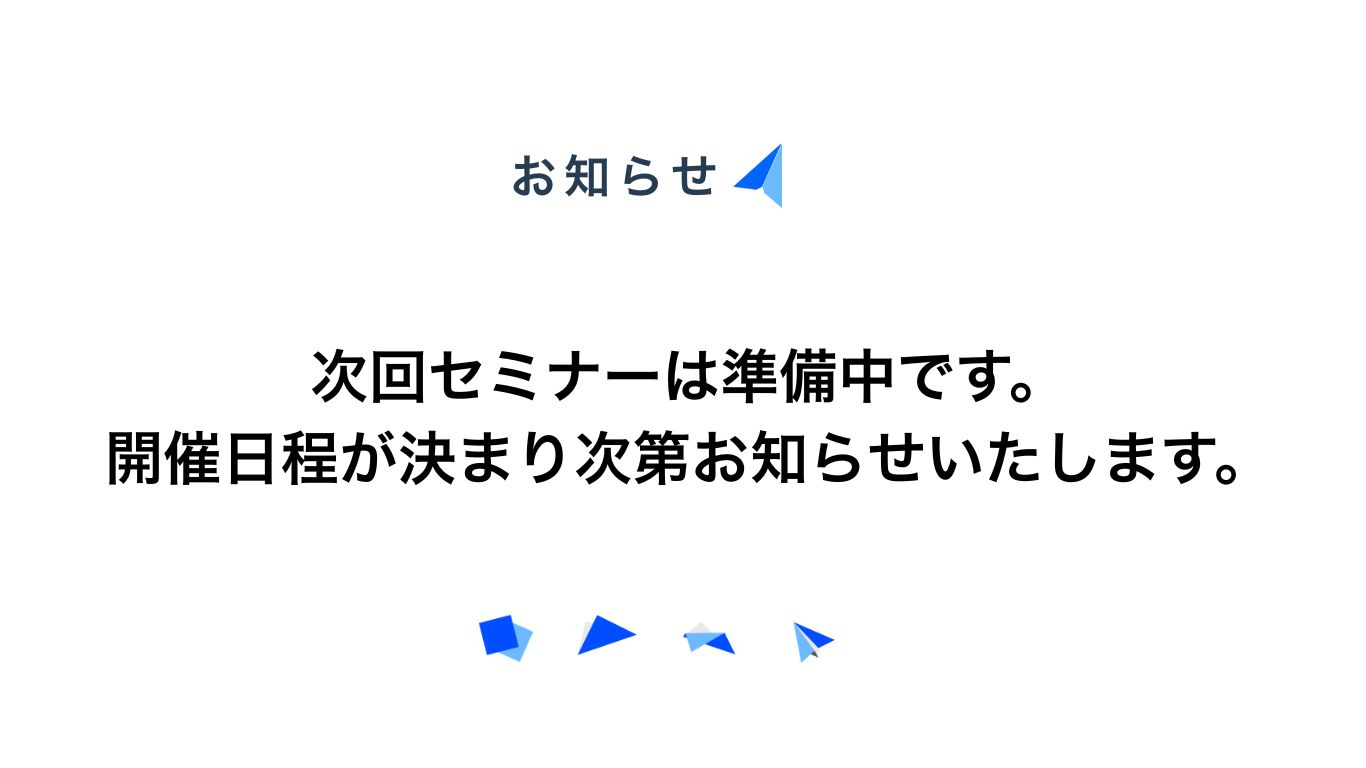―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は5月5日週に3.84円と、その前の週の3.96円から小幅に縮小した。週足では、3週続伸。前週比では0.42円の上昇となった。年初来リターンは7.6%安へ縮小した。5月のFOMCがタカ派的据え置きだったほか、米中高官による通商協議を控え、米英が貿易協定を締結したため楽観度が高まり、ドル円は約1カ月ぶりに146円台に乗せた。
- 5月FOMCは、市場予想通りFF金利誘導目標の据え置きが決定され、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は失業率とインフレの上昇リスクの高まりを指摘しつつ、関税によるインフレ警戒から利下げに急がない姿勢を強調した。トランプ大統領は引き続き、「ミスター遅過ぎ」と批判を続けるが、2024年8月に「労働市場のさらなる冷え込みを望まない」と発言した当時と比較し失業率は同程度であることを踏まえれば、パウエル議長率いるFedが労働市場のリスクを重視しない姿勢は、矛盾をはらむとも捉えられよう。
- トランプ政権が相互関税を発表してから約1カ月、貿易協定締結で一番乗りは英国となった。貿易協定の柱は、①英国への一律関税10%を維持、②英国に対する自動車関税25%→10%へ引き下げ、②鉄鋼・アルミ関税は撤廃、同金属の貿易圏創設、④米国産のエタノール、牛肉、シリアル、衣類、化学品、機械類などの英国市場へのアクセス拡大――など。米国は英国に対し貿易黒字を計上しており、鉄鋼輸入量も20位、新車輸入台数も1.2%程度となり、合意形成が貿易赤字国と比較して容易だったと考えられる。また、英国は足元でトランプ政権と価値観を共有し、①移民政策の厳格化、②英最高裁が男女の性別を2つと判断――に動く。しかも、トランプ大統領は貿易赤字国に対しては、「10%関税は低過ぎる」と発言。従って、英国との貿易協定内容が「モデルケース」となるとは言い難い。
- ベッセント財務長官とグリア米通商代表部(USTR)代表は5月10-11日、何立峰副首相とスイスで初の通商協議を行った。 トランプ氏は5月10日時点で「非常によい会談だった」と評価したが、中国商務部の報道官は5月8日に、引き続き相互関税など全ての関税の撤廃を要請していた。分散型予測市場プラットフォーム、ポリマーケットは5月10日時点で、5月内の合意の確率を60%以上織り込んでいたが、こうした見方は楽観的だろう。トランプ1期目では、2018年7月から対中関税を発動後、第1段階の暫定合意に達したのは2019年12月で、約1年半を要していた。
- 5月12日週に発表となる主な経済指標として、12日に日本3月国際収支、13日にユーロ圏と独の5月ZEW景況感指数、米4月消費者物価指数(CPI)、14日に日本4月企業物価指数が控える。15日は豪4月失業率、米4月小売売上高と生産者物価指数、米5月NY連銀とフィラデルフィア連銀の製造業景況指数、米新規失業保険申請件数、米4月鉱工業生産、米5月NAHB住宅市場指数、16日には日本Q1実質GDP成長率・速報値、米4月住宅着工件数、輸入物価指数、米5月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値、3月対米証券投資を予定する。
- その他、政治・中銀関連では12日にクーグラーFRB理事が経済見通しについての講演、13日は日銀の主な意見(4月会合分)、トランプ大統領の中東歴訪(サウジ、UAE、カタール、16日まで)、14日にジェファーソンFRB理事、ウォラーFRB理事の講演、SF連銀総裁の討論会参加を予定する。また、15日にはパウエルFRB議長が「金融政策見直し・枠組み見直し」について講演するほか、バーFRB理事の挨拶、16日に中村日銀審議委員の講演が控える。
- ドル円のテクニカルは、中立寄りへシフト。一目均衡表では転換線が基準線を上回り、遅行線がローソク足にかかるなど、三役逆転が消滅した。また、ローソク足は21日移動平均線だけでなく、基準線と転換線を抜けて週を終えた。テクニカル的には中立寄りへシフトしてきたと言えそうだ。今後は、2025年からの戻り局面で、RSIが割安感と割高感の中間にあたる50を超えてくると買い戻しが一服してきた流れが変わるのか、注目される。なお、5月9日にドル円が大幅上昇した局面でRSIは54.4をつけたが、翌日は52.5へ低下。年初来の最高は、3月27日の56.4となる。
- 以上を踏まえ、今週の上値は24年9月安値と25年1月高値の61.8%押しが近い147.00円、下値は21日移動平均線付近の143.30円と見込む。
1.先週のドル円振り返り=米英の通商合意締結でリスクオン、ドル円は約1カ月ぶりの146円乗せ
【4月28日~5月2日のドル円レンジ: 142.35~146.19円】
ドル円の変動幅は5月5日週に3.84円と、その前の週の3.96円から小幅に縮小した。週足では、3週続伸。前週比では0.42円の上昇となった。年初来リターンは7.6%安へ縮小した。5月のFOMCがタカ派的据え置きだったほか、米中高官による通商協議を控え、米英が貿易協定を締結したため楽観度が高まり、ドル円は約1カ月ぶりに146円台に乗せた。
5日、ドル円は軟調に推移。日本がゴールデン・ウィークの連休中、ドル円は徐々に下落し、ドル/台湾ドルが5月2日に続き急落(ドル安・台湾ドル高)が加速したことも材料視され、ロンドン時間に144円を割り込んだ。NY時間には、一時143.54円まで本日安値を更新。ただ、米5月ISM非製造業景気指数が市場予想を上回り、買い戻された。
6日、ドル円は売り優勢。東京市場がGWを受け休場のところ、FOMCを控えたポジション調整が入り、ロンドン時間から売りの流れが続いた。ベッセント財務長官が下院歳出委員会の小委員会で、中国とはまだ交渉していないと発言したことが意識されつつ、有力な貿易相手国と今週中にもディールを発表する可能性に言及したため、貿易ディール恐らく、早ければ今週にも発表と発言。強弱ミックスのコメントに揺れつつ、一時142.35円まで本日安値を更新した。
7日、ドル円は買い戻し。ベッセント財務長官がNY時間の6日にFOXニュースで中国代表とスイスで5月10-11日に会談する予定を明かし、ドル円の買いにつながった。中国外交部も何立峰副首相がベッセント氏と会談する予定を公表し、米中貿易戦争回避の期待から上昇の流れが継続。NY時間では、FOMCは市場予想通り据え置きのところ、パウエルFRB議長が労働市場より関税によるインフレ再燃の影響を重視する姿勢を示唆し利下げに急がないと発言すると、一時144.00円まで本日高値を更新した。
8日、ドル円は大幅高。トランプ大統領がトゥルース・ソーシャルにて、現地時間の7日夜に「尊敬される大国」との貿易協定について日本時間の午後11時から記者会見を開く予定と明かし、東京時間に145円台を回復した。ロンドン時間では一旦伸び悩んだが、トランプ氏の会見開始からは上げ足を加速。約1カ月ぶりに146円台に乗せ、一時146.18円まで上値を伸ばした。
9日、ドル円は前日からの上げ幅を削る展開。東京時間の序盤こそ日本3月実質賃金がマイナス幅を広げたため、一時146.19円まで上値を拡大したが、前日のドル高の反動や、明日からの米中貿易交渉を控えた警戒感から売りが入った。NY時間では一時144.83円まで本日安値を更新しつつ、145円前半で週を終えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!