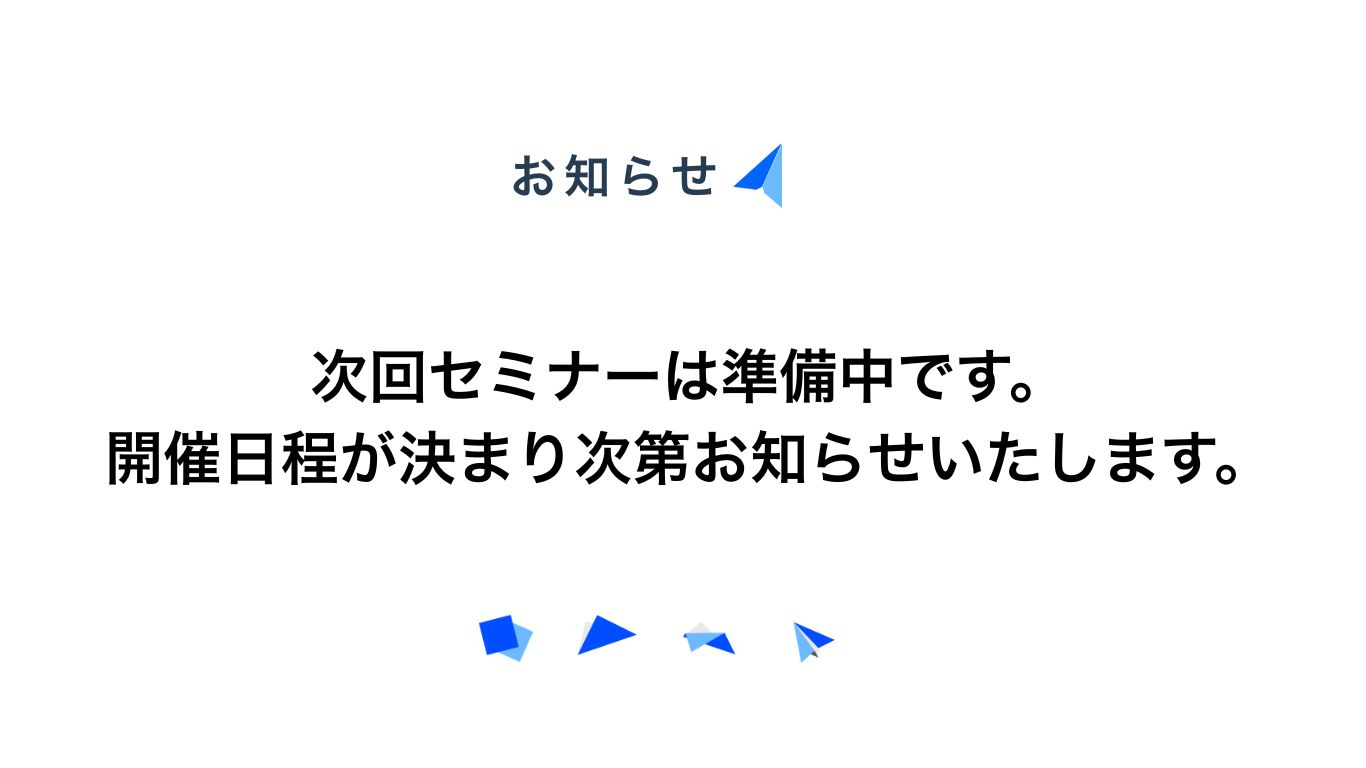―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は9月8日週に2.27円と、その前の週の2.35円から小幅に縮小した。週足では、3週続伸。前週比では0.25円の上昇となり、年初来リターンは前週の6.3%安から6.1%安へ縮小した。日銀が年内利上げを排除せずとブルームバーグが報じたため、一時146.31円まで週の安値を更新。しかし、米雇用統計の年次基準改定、米8月生産者物価指数(PPI)と米8月消費者物価指数(CPI)を受けても、下攻めせず。むしろ、自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障相が出馬するとの報道などのニュースを受け買い戻しが入り、146円~148円のレンジでの推移を続けた。
- 自民党総裁選をめぐり、9月15日時点では、茂木敏充前幹事長を筆頭に、小林鷹之経済安保相が次いで名乗りを挙げる状況。その他、高市氏のほか、小泉進次郎農相、林芳正官房長官が出馬の意向を固めたと報じられている。世論調査では高市氏がリード、小泉氏が後を追う状況。前週は、高市氏の過去の発言を踏まえ、同氏がリードとのニュースに反応し、ドル高・円安に振れてきた。ただし、高市氏と関係の深い麻生氏は消費税減税に反対の立場を表明済み。仮に総裁選で勝利しても、財政拡張路線を突き進むかは疑問が残る。
- 日米貿易合意に盛り込まれた対米投資5,500億ドル(約80兆円)をめぐり、赤沢亮正経済財政・再生相は9月12日に「円を売ってドルを直接買うような取引は基本的に発生しない」と明言した。外為特会や外為スワップを用いると説明しており、対米投資に伴うドル高・円安の思惑をけん制した格好だ。9月11日付の日米財務相共同声明で「いかなるマクロプルーデンス措置又は資本フロー措置も、競争上の目的のために為替レートを目標とはしないことに合意」との文言も確認できる。この文言は、対米投資5,500億ドルを口実とした円安を容認しないとする、米国の強い意志を反映したのではないか。
- 米連邦公開市場委員会(FOMC)が9月16~17日に行われ、日銀の金融政策決定会合が9月18~19日に開かれる。FOMCでは0.25%の利下げが見込まれており、注目は経済・金利見通しとパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の会見。経済・金利見通しで年内毎回の利下げが示されず、パウエル会見がタカ派的利下げとなれば、ドル円は上昇してもおかしくない。もっとも、ジャクソン・ホール会合の講演でパウエル氏が警戒したように、米8月雇用統計で労働市場の下振れリスクを確認しただけに、タカ派的利上げの決断には「雇用の最大化」へのリスクがつきまとう。
- 日銀は9月18~19日に金融政策決定会合を控え、今回は据え置く見通しだ。問題は次回10月29~30日会合での利上げを地ならしするか否か。日経新聞では、①新たな首相就任直後、②春闘への不透明感――などを理由に10月の利上げは困難と報じたが、植田総裁の会見内容が方向性を示すだろう。
- 9月15日週の主な経済指標として、15日に中国8月小売売上高と鉱工業生産、米9月NY連銀製造業景気指数、16日に米8月小売売上高と輸入物価指数、並びに鉱工業生産、米20年債入札17日に日本20年利付国債入札、日本8月貿易統計、英8月CPI、ユーロ圏8月HICP改定値、米9月住宅着工件数などを予定する。18日には豪Q2GDP、日本7月機械受注、豪8月失業率、米新規失業保険申請件数や米9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、19日は日本8月全国CPIが控える。
- その他、政治・中銀関連では、15日にラガルドECB総裁の発言(17・18日にも予定)、17日に、カナダ銀行の政策金利発表、FOMC政策金利発表(経済・金利見通し含む)とパウエルFRB議長の会見、トランプ大統領の英国訪問、18日に、イングランド銀行の政策金利発表、19日に日銀金融政策決定会合と植田総裁の会見、SF連銀総裁の発言を予定する。
- ドル円のテクニカルは中立寄りを維持。ドル円は、9月9日に一目均衡表の雲の下限を下抜け、一時146.31円まで下落したものの、50日移動平均線と8月安値が控える146.21円にサポートされた。逆に、9月11日には一目均衡表の雲の上限を抜ける場面があったが、米新規失業保険申請件数などにより押し下げられ、結局は一目均衡表の雲にすっぽり入り込んだままだ。ただし、抵抗線と化すかにみえた21日移動平均線がある147.56円を超えて週を終えており、上値をトライする余地を残す。RSIは8月4日以降、中立水準の50付近を維持しており、どちらに傾いてもおかしくない。
- 以上を踏まえ、今週の上値は心理的節目の150円ちょうど、下値は一目均衡表の雲の下限が近い146.70円と見込む。
1.前週のドル円振り返り=米指標と次期総裁をめぐる思惑で上下も、146~148円台のレンジ継続
【9月8~12日のドル円レンジ: 146.31~148.58円】
ドル円の変動幅は9月8日週に2.27円と、その前の週の2.35円から小幅に縮小した。週足では、3週続伸。前週比では0.25円の上昇となり、年初来リターンは前週の6.3%安から6.1%安へ縮小した。日銀が年内利上げを排除せずとブルームバーグが報じたため、一時146.31円まで週の安値を更新。しかし、米雇用統計の年次基準改定、米8月生産者物価指数(PPI)と米8月消費者物価指数(CPI)を受けても、下攻めせず。むしろ、自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障相が出馬するとの報道や世論調査でリードとのニュースを受け買い戻しが入り、146円~148円のレンジでの推移を続けた。
8日のドル円は買いが優勢。石破首相が9月7日に退陣する方向を示したため、ドル円は窓を開けて急伸し、一時148.58円まで週の高値を更新した。しかし、日本Q2実質GDP成長率・改定値が上方修正された結果が見直され、上げ幅を縮小した。
9日、ドル円は小動きを継続。ドル円は東京時間こそ小動きで、河野衆議員議員が日銀は利上げすべきとの考えを表明したものの、影響は限定的だった。東京時間の夕方にブルームバーグが日銀は政局を迎えながら年内利上げを排除せずと報じたため、一時146.31円まで週の安値を更新。147円割れでは底堅さを示し、NY時間に米雇用統計・非農業部門就労者数(NFP)の年次基準改定を受け、増加幅が91.1万人の下方修正を迎えると、再び146.50円台へ下落しつつ、その後は買い戻された。NY引け前には、一時147.57円まで本日高値を更新した。
10日、ドル円は買いの流れが継続。東京時間から、NY時間に米8月生産者物価指数(PPI)を控え、147円前半を中心とした推移を続けた。NY時間に入って米8月PPIが発表されると、市場予想より弱い結果が優勢で、ドル円は一時147.11円まで本日安値を更新。しかし、翌日に米8月消費者物価指数(CPI)を控え、下値は引き続き限定的だった。
11日、ドル円は乱高下。東京時間の終盤までは147円前半でのもみ合いを続けたが、高市前経済安保相が総裁選に出馬の方向で岸田前首相に報告との報道を受けて買いが膨らんだ。NY時間入りにかけ148円台を回復し、米8月CPI総合が前月比で市場予想を上回ると、一時148.19円まで本日高値を更新。しかし、米8月CPIコアが市場予想と一致したほか、スーパーコア(住宅を除くコアサービス)が前月以下にとどまり、かつ米新規失業保険申請件数が約4年ぶりの水準へ急増したため、すぐに下落に転じ、147円を割り込み一時146.99円まで本日安値を更新。その後は147円台を回復しつつ、戻りは限定的にとどまった。
12日、ドル円は買い戻し。東京時間に日米財務相の共同声明が発表されたものの、目新しい材料と判断されず、買い戻しが続いた。ロンドン時間に入り、高市氏が世論調査でリードとの報道が飛び出すと上値を拡大。NY時間には148円台を回復し、一時148.07円まで本日高値を更新も、上値は重く147円後半で取引を終えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!