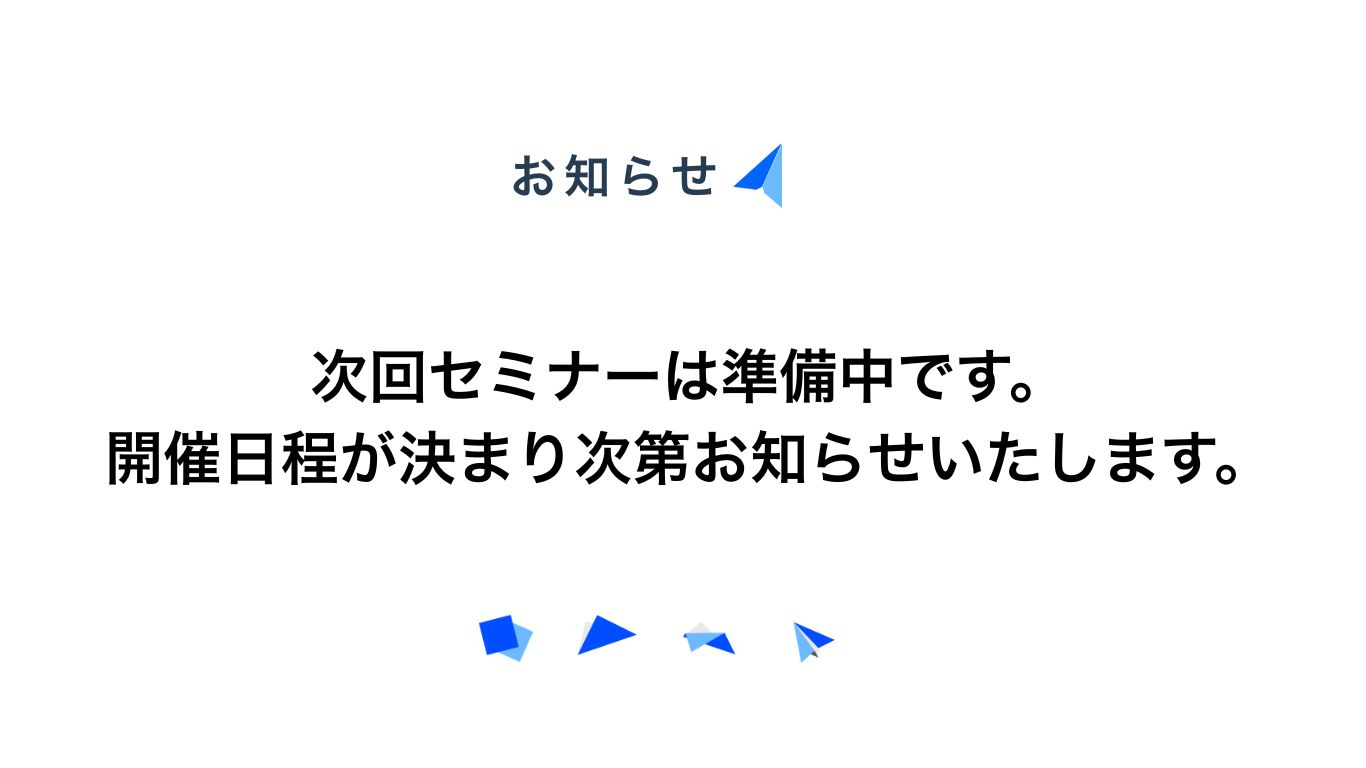中東情勢緊迫化で、「有事のドル買い」
13日にイスラエルはイラン各地の核施設や軍事施設などを中心として攻撃を実施し、イランも報復攻撃に出ました。そして先週末には米軍がイラン国内の3カ所の核施設を空爆しました。イランもカタールの米軍基地にミサイルを発射し報復したが、イランの報復攻撃は控え目と受け止め、米軍の攻撃はエスカレートせず、トランプ米大統領が発表したイランとイスラエルの停戦合意をイラン・イスラエルともに受け入れる姿勢を示し、攻撃の応酬はひとまず沈静化しています。
今回の中東リスクに為替相場では「リスク回避の円買い」ではなく、「有事のドル買い」で反応しました。米軍がイランを攻撃したことを受けて週明け23日のドル円は一時148円近辺までドル高・円安が進みました。
「有事のドル買い」
有事のドル買いとは、外国為替取引に関する格言のひとつです。 例えば、戦争等の有事に際して、為替相場がどのように変動していくかということは見通しがつきにくい部分です。 それで、何があっても良いように、流動性のある米国の通貨であるドルを買っておけば安心であるとう経験的な法則に基づいています。
「リスク回避の円買い」
地政学リスクが高まったり、世界経済が悪化したり投資家のリスクオフムードが強まると、投資家は円に資金を避難させる傾向があります。その根拠の1つになっているのが、日本の持つ世界最大の対外純資産です。
近年の「リスク回避の円買い」
近年は有事の際、米ドルより日本円が買われることが多かったです。2017年4月に起こった米軍のシリア攻撃、その後の朝鮮半島との緊張の高まりなどではドル円がドル安・円高に傾きました。特に記憶に残るのは、東日本大震災が起こった2011年3月11日は83円ほどで推移していたドル円は、7月中旬には79円台に突入し、10月末には75円台と円の過去最高値をつけました。あれほどの大災害に見舞われたにも関わらず、円が売り込まれることもなく、反対に過去最高値まで買われたわけです。
今回、なぜ円買いではなかったか?
要因は主に二つあげられます。
一つは、中東リスクを背景に原油価格が一時急騰したことです。輸入の約 25%が鉱物性燃料で構成される日本にとって原油価格急騰は死活問題であり、原油高は日本の貿易赤字を拡大させることで円売り圧力が強まりました。この動きはウクライナ・ロシアの戦争が始まった時にも見られました。日本の原油輸入量に占める中東諸国の比率は、最新の4月時点 で93.7%となっています。
もう一つは積み上がった円ロングポジションです。米商品先物取引委員会(CFTC)のIMM通貨先物非商業部門の取り組み状況によると、17日時点での円買い持ちは差し引きで約13万枚強となっています。過去最大を記録した4月下旬のピーク時の18万枚弱から8週連続で減少したが、依然として高い水準と言えます。「リスク回避」というのは、「リスクのポジションを解消し中立化する」とも言えるので、今回円買いではなく円の投機ポジションを解消する円売りが進んだことも納得できます。
中東情勢が沈静化しても、米国の関税政策や財政懸念、景気減速に利下げ観測の高まり、日本の利上げ観測後退など、多数の不透明要因があります。投機の円買いはまだ高水準でもあり、円相場は不安定が続きやすいです。
【免責事項・注意事項】
本コラムは個人的見解であり、あくまで情報提供を目的としたものです。いかなる商品についても売買の勧誘・推奨を目的としたものではありません。また、コラム中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。
※本記事は2025年6月28日に「いまから投資」に掲載された記事を、許可を得て転載しています。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!