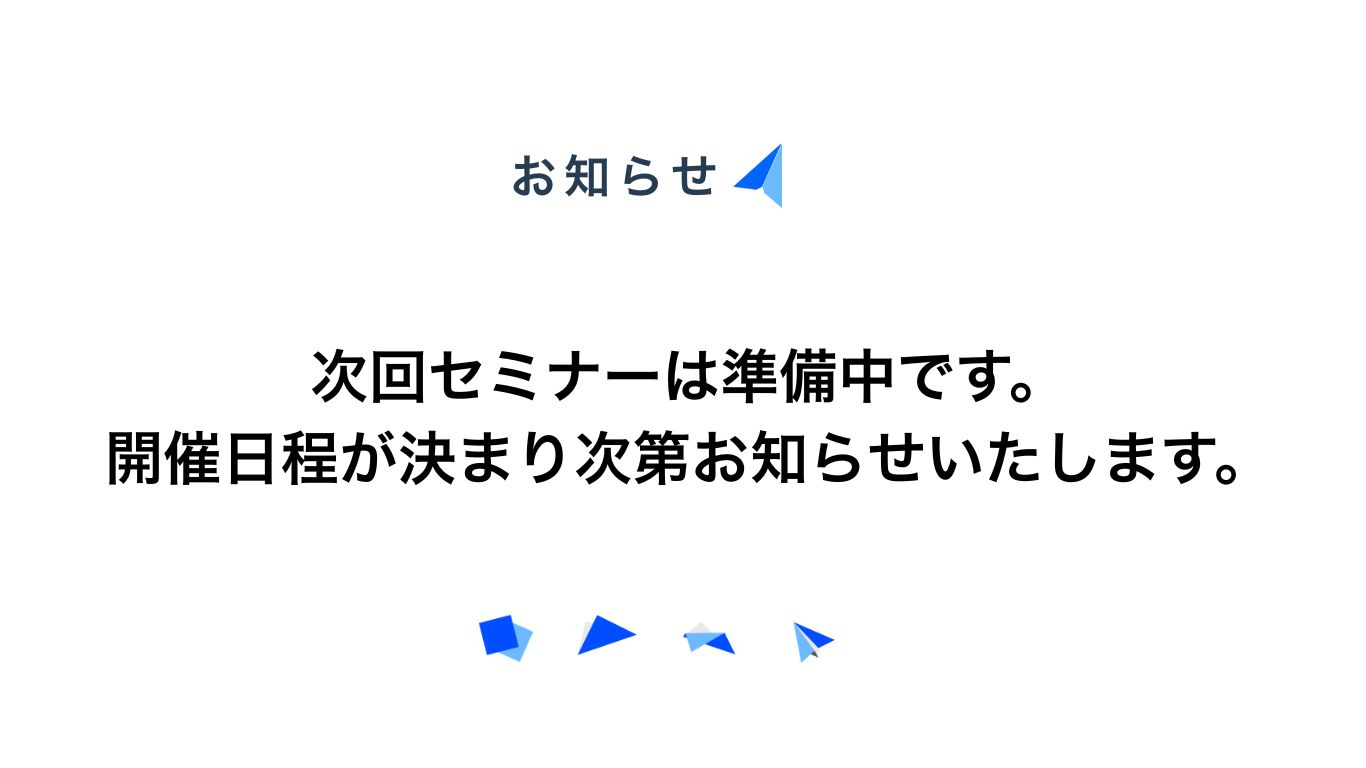―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は20日週に2.79円、その前の週の3.24円から縮小した。週足では反発。前週比では2.22円の上昇となり、年初来リターンは前週の4.2%安から2.8%安へ下げ幅を縮小した。ドル円は高市政権発足を受けて、上値を試す流れを迎えた。米中対立をめぐる懸念も、トランプ大統領の発言を受けて限定的。ブルームバーグが10月利上げの可能性を否定したこともドル円の押し上げに寄与し、一時153.06円と約2週間ぶりの153円に乗せ、米9月消費者物価指数(CPI)が予想以下でも下げ渋った。
- 第5回目となる米中閣僚協議が10月25~26日にマレーシアで行われ、両国は枠組み合意に至った。詳細については不明だが、ベッセント財務長官や中国の李成剛・国際貿易交渉代表によれば、対中関税100%の上乗せや、レアアースの輸出強化の見送りが期待される。10月30日に予定する米中首脳会談では、米中閣僚協議がたたき台となり、緊張緩和が予想通り演出されれば、ドル円の上昇を下支えしうる。なお、事前に中国側がトランプ政権に台湾の独立に反対する立場を表明する計画と伝えられ、一部では貿易合意のため、トランプ政権が台湾で中国に譲歩するとの観測が広がったが、ルビオ国務長官はこれを否定した。
- 10月28~29日の米連邦公開市場員会(FOMC)では、前回に続き、0.25%の利下げを決定する見通しだ。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は10月14日、労働市場の下方リスクに言及。米8月雇用動態調査では失業者1人当たりの求人件数が1件を割り込み、州ベースの米新規失業保険申請件数は増加しつつある。加えて、米9月消費者物価指数(CPI)は市場予想で下振れした。一連の結果を踏まえれば、利下げを行うだろう。その他、準備預金残高が、金融市場が推定する「十分な水準」とされる3兆ドルを割り込み始めている。2019年秋のような短期金利の急伸を回避すべく、量的引き締め(QT)の終了を決定してもおかしくない。
- 日米首脳会談を10月28日に控え、29~30日には日銀金融政策決定会合を予定する。ベッセント財務長官も訪日するなか、8月13日や10月15日に発言したように、同氏が日銀金融政策決定会合を直前に控え、同様の見解を表明すれば、米国から圧力の高まりを印象づけるに違いない。もっとも、9月会合以降、政策委員の発言ラッシュが相次いだが、植田総裁や内田・氷見野副総裁は10月利上げの布石を打たなかったと言える。ドル円が153円を超える状況で円安を警戒するなら利上げが視野に入るが、高市政権発足直後であり、12月の補正予算提出なども控え、10月は据え置きを決定するのではないか。
- ただし、据え置きだとしても、ドル円の一段高を抑制する意図が働くなら、利上げ票が前回の2票から3票へ増え12月利上げへつなげる、展望レポートでも事前報道通り25年度の国内総生産(GDP)見通しが上方修正されるなど、円安を抑制する手立ても意識される。ドル円の方向性の決め手となる植田総裁の会見では、同氏が就任して以来、20回中、終値ベースの前日比で5回上昇してきた。今回の植田氏の会見内容は、高市政権の日銀の金融政策運営にどこまで関与しているのか、見極める機会を与えてくれそうだ。
- 10月27日週の経済指標は、27日に日本9月企業向けサービス価格指数、独10月Ifo企業景況感指数、28日に米10月消費者信頼感指数、29日に豪9月CPI、30日にユーロ圏と独のQ3GDP速報値、ユーロ圏と独10月失業率、31日に日本9月失業率と有効求人倍率、鉱工業生産、並びに日本10月東京都区部CPI、中国10月製造業PMI、ユーロ圏10月統合消費者物価指数(HICP)を予定する。
- その他、政府・中銀関連では、29日にカナダ銀行の政策金利発表、FOMCの政策金利発表とパウエルFRB議長の会見、30日に日銀の政策金利発表と植田日銀総裁会見、ECBの政策金利発表とラガルドECB総裁の会見、31日にダラス連銀総裁とクリーブランド連銀総裁の発言を予定する。
- ドル円のテクニカルは、極めて強い地合いにある。一目均衡表は三役好転を保ち、前週は150円を下抜けることはなく、週後半は2024年9月安値と2025年1月高値の38.2%押しにあたる151.51円の水準も割り込もなかった。RSI(14日)やMACDもゴールデン・クロスを形成。ただ、10月10日に153.28円まで高値を付けた当時、RSIは割高感の節目70を超え、その後に調整に入った。今回も同様となるのか、あるいは2022~24年当時のように80超えを試すのか、見極めが必要となりそうだ。
- 以上を踏まえ、今週の上値の目途は2024年7月と2025年1月の高値を結んだトレンドラインの154.50円、下値は10月21日安値付近の150.50円と見込む。
1.ドル円振り返り=米中対立懸念を乗り越え高市政権発足を受けドル円は再び153円乗せ
【10月20日~24日のドル円レンジ:150.27~153.06円】
ドル円の変動幅は20日週に2.79円、その前の週の3.24円から縮小した。週足では反発。前週比では2.22円の上昇となり、年初来リターンは前週の4.2%安から2.8%安へ下げ幅を縮小した。ドル円は高市政権発足を受けて、上値を試す流れを迎えた。米中対立をめぐる懸念も、トランプ大統領の発言を受けて限定的。ブルームバーグが10月利上げの可能性を否定したこともドル円の押し上げに寄与し、一時153.06円と約2週間ぶりの153円に乗せ、米9月消費者物価指数(CPI)が予想以下でも下げ渋った。
20日のドル円は買い戻し。トランプ大統領が19日に習国家主席が米国とディールに前向きと発言し、ドル円は買い戻しでスタートし、序盤に一時151.20円と本日高値を更新した。その後は伸び悩み、自民・維新が連立合意へとの報道や、高田審議委員のタカ派な見解への影響も、限定的。日銀が10月29-30日の金融政策決定会合で公表する展望レポートで、2025年度の実質国内総生産(GDP)見通しを小幅に引き上げる可能性と報じられると、一時150.27円まで本日安値を更新。ただ、下値も堅く、ハセットNEC委員長、NY序盤にCNBCに出演し政府機関閉鎖が今週中に終了する可能性に言及したこともサポートとなった。トランプ氏が中国とディール不成立では対中関税100%上乗せすると述べたが反応薄で、150円半ばでの推移を続けた。
21日、ドル円は上昇。臨時国会での首相指名選挙前、高市新政権で財務相に片山氏、経産相に赤沢氏、防衛相に小泉氏が就任する見通しと報じられるなか、150円半ばから151円台を超えていった。氷見野副総裁が講演で金融政策に言及せず、第104代首相に高市早苗氏が選出されたタイミングでは、むしろ日経平均の高市首相誕生に伴うセル・ザ・ファクトにつれ、ドル円は上げ幅を縮小。その後、ブルームバーグが10月日銀金融政策決定会合で利上げに急ぐ必要性は乏しいと報じると、利上げ期待のはく落から右肩上がりの展開に入った。財務相に就任する片山さつき氏が為替はファンダメンタルズを反映し安定推移が望ましいと発言する中でも上値を広げ、NY序盤には、一時152.17円まで本日高値を更新。トランプ大統領、米中首脳会談が実現しない可能性に言及したが、引き続き影響は限定的だった。
22日、ドル円は堅調に推移。序盤は売り先行で、151.49円まで本日安値を更新したが、その後は151円後半を中心とした推移を続けた。城内経済財政相が「強い経済成長と物価安定の両立へ向け、適切な金融政策実施が重要」と述べたが、反応は限定的。高市首相が片山財務相に「経済再生と財政健全化両立」を指示したと報じられたが、このニュースにも大きく反応しなかった。NY時間には一時152.02円まで本日高値をつけたが、トランプ政権が米国製ソフトウェアや関連製品の中国向け輸出の制限を検討との報道を受け、151円半ばへゆるむ場面がみられたものの、押し目を拾われやすかった。ホワイトハウスが現地時間22日引け直前にロシアに即時停戦を求め、露石油大手ロスネフチとルクオイルに制裁を課したが、リスクオフを迎えることはなかった。
23日、ドル円は上値を試す展開。東京時間の序盤から高市トレードが復活したようで買いが先行し、152円半ばを超えて右肩上がりを示した。NY時間には、一時152.80円まで本日高値を更新。翌24日に米9月CPIの発表を予定しながら、ドル高・円安の流れが続いた。
24日、ドル円は買い優勢。9月全国CPIへの影響は限定的で、前日に続き買いでスタートした。トランプ大統領がトゥルース・ソーシャルでカナダとの通商協議打ち切りに言及し、片山財務相がベッセント財務長官と24日に電話協議を行った後で27日にも会談を開くと報道が流れたものの、152.70円台へゆるんだ程度。ロンドン時間入りには、1週間ぶりに153円に乗せ、一時153.06円まで週の高値をつけた。NY入りに米9月CPIが発表され、市場予想以下だったため一時152.23円まで本日安値を更新。米10月S&P総合PMI速報値などが市場予想を上回ったため、すぐに下げ幅を縮小しつつ、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値が市場予想以下となり、以降は152円後半での推移を続けた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!