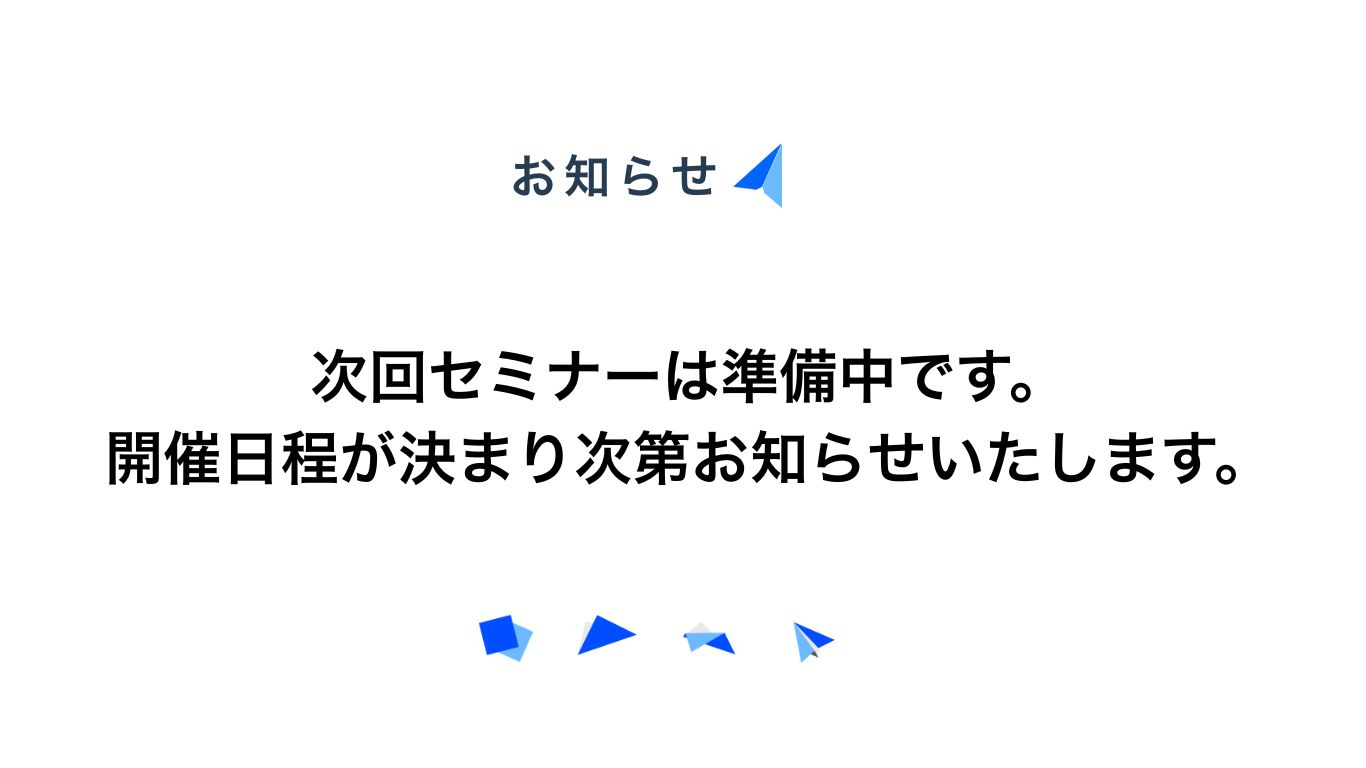―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は10月27日週に2.91円と、その前の週の2.79円から小幅に拡大した。週足では続伸。前週比では1.15円の上昇となり、年初来リターンは前週の2.8%安から2.1%安へ下げ幅を縮小した。トランプ政権が訪日する流れで、ベッセント財務長官が2度にわたって日銀の利上げと円安是正を促す見解を表明したため、ドル円は一旦下落した。しかし、FOMCが利下げを行ったもののパウエルFRB議長が12月利下げに否定的な発言を行い、日銀が一部の期待に反し据え置きを決定し利上げ票も前回通りにとどまり、ドル円は上値を試す展開。植田総裁が利上げの決め手として春闘を挙げたため、12月利上げの期待も一部で剥落した結果、ドル円は2月13日以来の154円を超えていった。
- 10月28~29日開催の米連邦公開市場員会(FOMC)では、前回に続き、0.25%の利下げを決定、12月1日からの量的引き締め(QT)も決定した。ただし、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、12月の利下げは既定路線ではないと強調。労働市場にも悪化の兆候は見られないとタカ派的な見方を寄せた。FF先物市場での12月FOMCでの利下げ織り込み度は10月31日に一時63%と、前週の96.4%から低下。12月利下げに否定的とも言えるパウエル発言が並んだものの、未だに利下げ予想が優勢な理由は、①政府機関閉鎖による米指標の弱含み、②9月FOMCもタカ派的な発言が優勢だったものの、10月に利下げを決定――などが意識されているためだろう。
- FRBは10月31日、短期金融市場の混乱に対応するため、常設レポファシリティ(SRF)を活用し、2回にわたるオペレーションを通じて、金融機関に過去最大となる503.5億ドルの資金を供給した。これは、翌日物担保付き資金調達金利(SOFR)が、10月30日に続き31日にFF金利誘導目標の上限である4.0%を突破したことを受けた緊急対応。10月に入り、SOFRはFF金利誘導目標の上限を上回るケースが目立ち、短期資金市場におけるストレスの高まりと、金融システム全体での現金供給の逼迫を示す。月末要因で資金不足に陥った可能性は否定できないが、今後も続くようならば、FRBが再び市場に流動性を供給する(=事実上の金融緩和)の必要性が高まり、ドル円を押し下げる可能性に留意すべきだろう。
- 日銀は10月29~30日の金融政策決定会合で、据え置きを決定した。利上げ票が9月に続き2人にとどまったほか、植田総裁が利上げに向け春闘を重視する姿勢を打ち出すと、ドル円は急伸。植田氏は、春闘の初動を見たいと述べたほか、12月の予算編成、並びに政治環境に関係なく、納得できれば利上げは可能との見解を寄せ、12月利上げへの道筋を確保したように見える。しかし、「責任ある積極財政」を掲げる高市政権は利上げに慎重とみられ、2026年1月までに1回利上げしたとしても、その後の日銀の利上げの道筋には不透明感が残る。
- 11月3日週の経済指標は、3日に中国10月RatingDog製造業PMIを始め、ユーロ圏や独、英、米の製造業PMI改定値、米10月ISM製造業景況指数、5日はNZQ3失業率、中国10月RatingDogサービス業PMI、ユーロ圏や独、英、米の総合PMI改定値(サービス業含む)、米10月ADP全国雇用者数、米10月ISM非製造業景況指数を予定する。6日には日本9月実質賃金、米10月チャレンジャー人員削減予定数、7日には中国10月貿易収支、米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値が控える。
- その他、政府・中銀関連では、3日にクックFRB理事、サンフランシスコ連銀総裁の発言、4日に豪準備銀行の政策金利発表、ラガルドECB総裁やボウマンFRB副議長の発言、ニュージャージー州とバージニア州の知事選およびNY市長選、5日に日銀の9月分の金融政策決定会合議事要旨公表、米最高裁判所のトランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論の開始を予定する。6日にイングランド銀行の政策金利発表のほか、ウォラーFRB理事を始めバーFRB理事、NY連銀総裁、クリーブランド連銀総裁、フィラデルフィア連銀総裁、講演の発言が目白押しとなる。7日は、NY連銀発表の米10月インフレ期待の他、ミランFRB理事を始めNY連銀総裁、セントルイス連銀総裁の発言を予定する。なお、米国では11月2日から、冬時間に移行した。
- ドル円のテクニカルは、極めて強い地合いを維持。一目均衡表は三役好転を保ち、2024年7月高値と2025年1月の高値を結んだトレンドラインを超えた。ただ、トランプ政権発足後、RSIは割高感の節目70前後では、調整する地合いを引き継いでいる。今回も同様となるのか、あるいは2022~24年当時のように80超えを試すのか、引き続き見極めが必要となりそうだ。
- 以上を踏まえ、今週の上値の目途は心理的節目の155.50円、下値目途については21日移動平均線が近い151.90円と見込む。
1.ドル円振り返り=タカ派FOMCとハト派日銀で、ドル円は2月中旬以来の154円乗せ
【10月27日~31日のドル円レンジ:151.54~154.45円】
ドル円の変動幅は10月27日週に2.91円と、その前の週の2.79円から小幅に拡大した。週足では続伸。前週比では1.15円の上昇となり、年初来リターンは前週の2.8%安から2.1%安へ下げ幅を縮小した。トランプ政権が訪日する流れで、ベッセント財務長官が2度にわたって日銀の利上げと円安是正を促す見解を表明したため、ドル円は一旦下落した。しかし、FOMCが利下げを行ったもののパウエルFRB議長が12月利下げに否定的な発言を行い、日銀が一部の期待に反し据え置きを決定し利上げ票も前回通りにとどまり、ドル円は上値を試す展開。植田総裁が利上げの決め手として春闘を挙げたため、12月利上げの期待も一部では落した結果、ドル円は2月13日以来の154円を超えていった。
27日のドル円は買い先行後に失速。26日までマレーシアで行われた米中閣僚協議で、枠組み合意に達したとの報道を受け、米中首脳会談をめぐる楽観的な見方が流れ、東京時間にドル円は一時153.26円と10月10日の高値153.28円に迫った。もっとも、その後は日米首脳会談や米中首脳会談、FOMCや日銀会合を控え、上げ幅を縮小した。日米財務相会談が行われたが、片山財務相が為替や日銀の金融政策は話題にならなかったと発言したため、影響は限定的だった。
28日のドル円は売り先行。日米首脳会談を控え、ドル円は軟調に推移するなか、米財務省が日米財務相会談でベッセント財務長官が日銀の利上げと円安是正を促したと示唆される声明を公表し、一時151.76円まで本日安値を更新。2024年9月安値と2025年1月高値の38.2%押しに当たる151.51円を手前には買い戻され、片山氏が金融調節について言及はなかったとベッセント見解を否定すると、一時は152.37円まで本日高値をつけた。
29日、ドル円は続落。日銀金融政策決定会合を控えたベッセント氏の見解に続き、本人が離日にあたり、あらためて日銀の利上げと円安是正を望む示唆を与えると、ドル円は一時151.54円まで週の安値を付けた。しかし、前日に続き151.51円の抵抗線に阻まれ、買い戻し。NY時間にはFOMCで利下げと量的引き締め(QT)の停止を決定したものの、パウエルFRB議長が12月の利下げに否定的な発言を行ったためドル円は買いへ旋回し、153円を突破し一時153.06円まで本日高値をつけた。
30日、ドル円は一段高。前日のFOMCの流れを引き継ぐなか、日銀金融政策決定会合前にドル円は小動きだったが、市場予想通り据え置き決定が発表されたところ、利上げ票が前回に続き2回にとどまった結果、ドル円は買いが吹き上がった。一部で、ベッセント見解を受けた利上げ期待もあり、ショートが急激に巻き戻されたもよう。植田総裁の会見では、春闘まで見極める姿勢が嫌気され、その後は右肩上がりの展開となり154円も突破。東京時間で報じられた米中首脳会談での合意報道も後押しし、NY時間では一時154.45円と2月13日以来の高値をつけた。
31日、ドル円は堅調な流れを維持。10月東京都区部CPIが上向き、片山財務相が口先介入を行ったものの、一時153.65円まで本日安値を更新する程度で、その後は切り返した。ロンドン時間には、一時154.42円まで本日高値を更新。以降、154円割れは限定的で堅調な推移を保った。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!