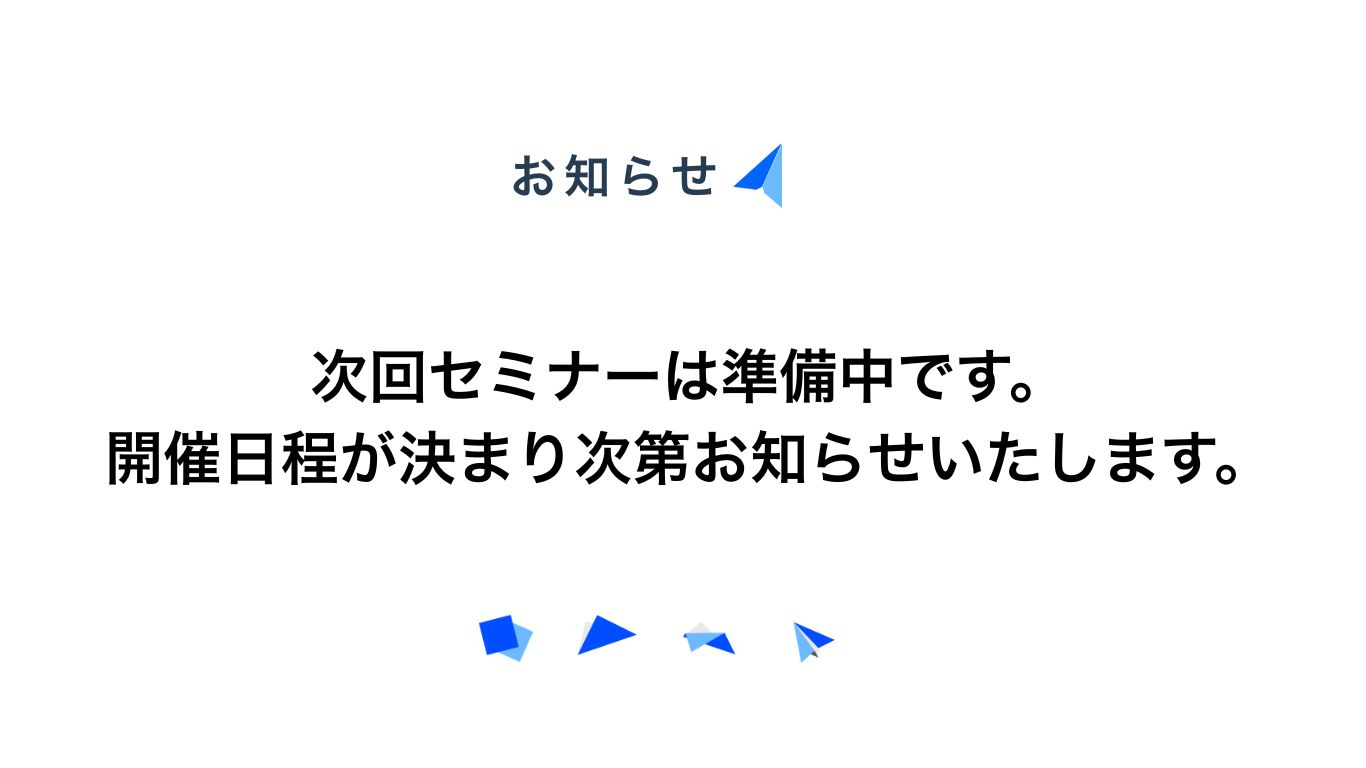―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は7月14日週に2.34円と、その前の週の3.30円から縮小した。週足では、続伸。前週比では1.42円の上昇となった。年初来リターンは前週の6.3%安から5.4%安へ縮小した。トランプ大統領が引き続き、欧州連合(EU)やメキシコに新たな関税率30%を課す方針を表明したほか、ロシアが50日以内に停戦合意しなければ、ロシアの貿易相手国に対し100%の二次関税を発動する方針を示し、インフレ警戒からドル買いが優勢となった。米6月消費者物価指数(CPI)が前月から加速したことも、材料視。しかし、トランプ氏がパウエルFRB議長を解任するとの報道が飛び出し、すぐにトランプ氏が否定するなど147円割れから148円後半まで買い戻されるなど、乱高下した。
- 参院選が7月20日に行われ、与党が過半数割れを迎えた。もっとも、石破首相が続投の意向を表明するなど海外勢が懸念した不確実性が高まらず、ドル円は下落(円買い戻し)で反応。もっとも今後、政治は流動化する懸念がある。両院議員総会開催や総裁解任論など、与党内分裂の懸念も残す。加えて、レームダックが否めない石破政権が米国との通商協議で日本に利する合意を引き出すことは一段と困難と想定され、日本独自の円買い材料は限定的と言わざるを得ない。
- 一方で、トランプ政権がパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長に対し、FRB本部の改修25億ドルを理由に辞任圧力を強めている点は懸念材料。同問題がパウエル氏の解任につながるとは想定しづらいが、 国家首都計画委員会(NCPC)とFRBの対立に伴う不確実性が懸念される。もっとも、トランプ政権のパウエル氏への圧力は①ドル高圧力のガス抜き、②FRB改革へのメッセージ――とも考えられよう。特に、次期FRB議長候補のウォーシュFRB元理事が新たに「米財務省―FRB協定」の必要性を唱えている点は、低金利政策を望むトランプ政権の意図を反映していると解釈でき、留意すべきだ。
- トランプ氏は、7月18日、「米国におけるステーブルコインの国家的イノベーションの指導と確立法:通称、GENIUS法案)」に署名した。これは、ドルなど法定通貨に連動する暗号資産、ステーブルコインに対して、規制枠組みを確立した初めての法律と報じられている。同法は、ステーブルコインの発行業者に米国債などドル資産の担保の義務付けが狙いのひとつ。米国債需要拡大を通じ米金利低下につながる期待がある。
- 7月21日週の主な経済指標として、23日に米6月中古住宅販売件数、24日にユーロ圏と独の7月総合PMI速報値(製造業・サービス業含む)、米新規失業保険申請件数、米7月総合PMI速報値(製造業・サービス業含む)、米6月新築住宅販売件数、25日に日本7月東京都区部CPIと6月企業向けサービス価格指数、独7月IFO企業景況感指数、米6月耐久財受注を予定する。
- その他、政治・中銀関連では、22日に豪準備銀行の金融政策会合議事要旨公表、ベイリー英中銀総裁の発言、パウエルFRB議長の講演(ブラックアウト期間中であり金融政策に言及しない見通しで、講演テーマは資本規制)、24日に欧州中央銀行(ECB)の政策金利発表とラガルドECB総裁の会見を予定する。
- ドル円のテクニカルは、強気へシフト。ドル円は、一目均衡表で三役好転を形成し、5月12日の高値でテクニカル的に重要な節目である148.65円を上抜けて週を終えた。24年9月16日安値の139.58円と25年1月3日高値の158.88円の半値押しにあたる149.23円、200日移動平均線がある149.63円を超えていけば、150円突破が射程圏内に入る。しかし、やはり上値の重さは否定できない。参議院選後は、再び5月12日の高値148.65円で阻止された。投機筋の円先物のネット・ロングが一定程度取り崩された事情があるほか、来週29~30日のFOMC、30~31日の日銀金融政策決定会合を控え、動意に乏しくなる場合もありそうだ。
- 以上を踏まえ、今週の上値は2024年9月と2025年高値の半値押しが近い149.30円、下値は21日移動平均線が近い146円ちょうど付近と見込む。
1.前週のドル円振り返り=トランプ関税と堅調な米指標で約3カ月ぶり149円乗せも、パウエル解任騒動で乱高下
【7月14~18日のドル円レンジ: 146.85~149.19円】
ドル円の変動幅は7月14日週に2.34円と、その前の週の3.30円から縮小した。週足では、続伸。前週比では1.42円の上昇となった。年初来リターンは前週の6.3%安から5.4%安へ縮小した。トランプ大統領が引き続き、欧州連合(EU)やメキシコに新たな関税率30%を課す方針を表明したほか、ロシアが50日以内に停戦合意しなければ、ロシアの貿易相手国に対し100%の二次関税を発動する方針を示し、インフレ警戒からドル買いが優勢となった。米6月消費者物価指数(CPI)が前月から加速したことも、材料視。しかし、トランプ氏がパウエルFRB議長を解任するとの報道が飛び出し、すぐにトランプ氏が否定するなど147円割れから148円後半まで買い戻されるなど、乱高下した。
14日にドル円は売り先行を経て買い戻し。東京時間は、トランプ氏が12日に欧州連合(EU)やメキシコへの30%の関税発動に言及したため、リスクオフを迎え一時146.85円まで下落して週間安値を記録した。しかし、すぐに切り返し147円台を回復し、NY時間には買いが加速。トランプ氏が、50日以内に停戦合意しなければロシアの貿易相手国を対象に100%の「二次関税」を課す意向を表明した結果、インフレ警戒が再燃し一時147.52円まで本日高値を付けた。
15日、ドル円は上値を広げる展開。東京時間に、早川元理事が日銀の追加利上げについて物価高を受け早ければ10月と発言したが、米6月CPIの公表を前に反応薄だった。NY時間には、米6月CPIが概ね市場予想と一致したものの、前月から加速したためドル円が上値を追う展開に突入。5月12日の高値148.65円のテクニカル的な節目をあっさり抜け、一時149.02円まで切り上げ約3カ月ぶりの高値をつけた。
16日、ドル円は上げ幅縮小を経て乱高下。東京時間に、トランプ大統領が現地時間15日夜に医薬品への関税を8月1日から発動し、徐々に引き上げていく方針を示したため、ドル円は一時149.19円まで上昇し約3カ月ぶりの高値をつけた。もっとも、その後は伸び悩み。参議院選を前にバラマキや減税など財政悪化が懸念されるなか、格付け会社フィッチが参院選後の日本国債格付けのリスクを指摘した流れから、ドル円の下落も限定的。米6月生産者物価指数(PPI)が市場予想以下にとどまり売りが入っても下値が堅かったところ、トランプ氏がパウエルFRB議長を解任すべく書簡の草稿を米共和党議員に示したと報道が飛び出し、147円を割り込み一時146.91円まで当日安値を更新した。しかし、トランプ氏がすぐに否定したため、147円後半で取引を終えた。
17日、ドル円は買い戻し。東京時間から買いが優勢で、参院選で自民党と公明党の与党が苦戦を強いられているとの報道も、意識された。NY時間には、米6月小売売上高や米新規失業保険申請件数、米7月フィラデルフィア連銀製造業景気指数などそろって市場予想を上回り、一時149.09円まで本日高値を更新も、上値は重かった。ウォーシュ元FRB理事が1951年の米財務省・FRB協定に言及したが、影響は抑えられた。
18日、ドル円は堅調。ウォラーFRB理事が7月利下げを支持する発言を行ったが反応薄で、日本6月全国CPIが市場予想以下となり、ドル買いが入った。参院選で与党が過半数割れの可能性が引き続き意識され、ロンドン時間の入りに一時148.89円まで本日高値を更新。上値の重さが引き続き意識されたが、上値も限定的だった。ベッセント財務長官が石破首相と会談したが、特に新しい材料は飛び出すことはなかった。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!