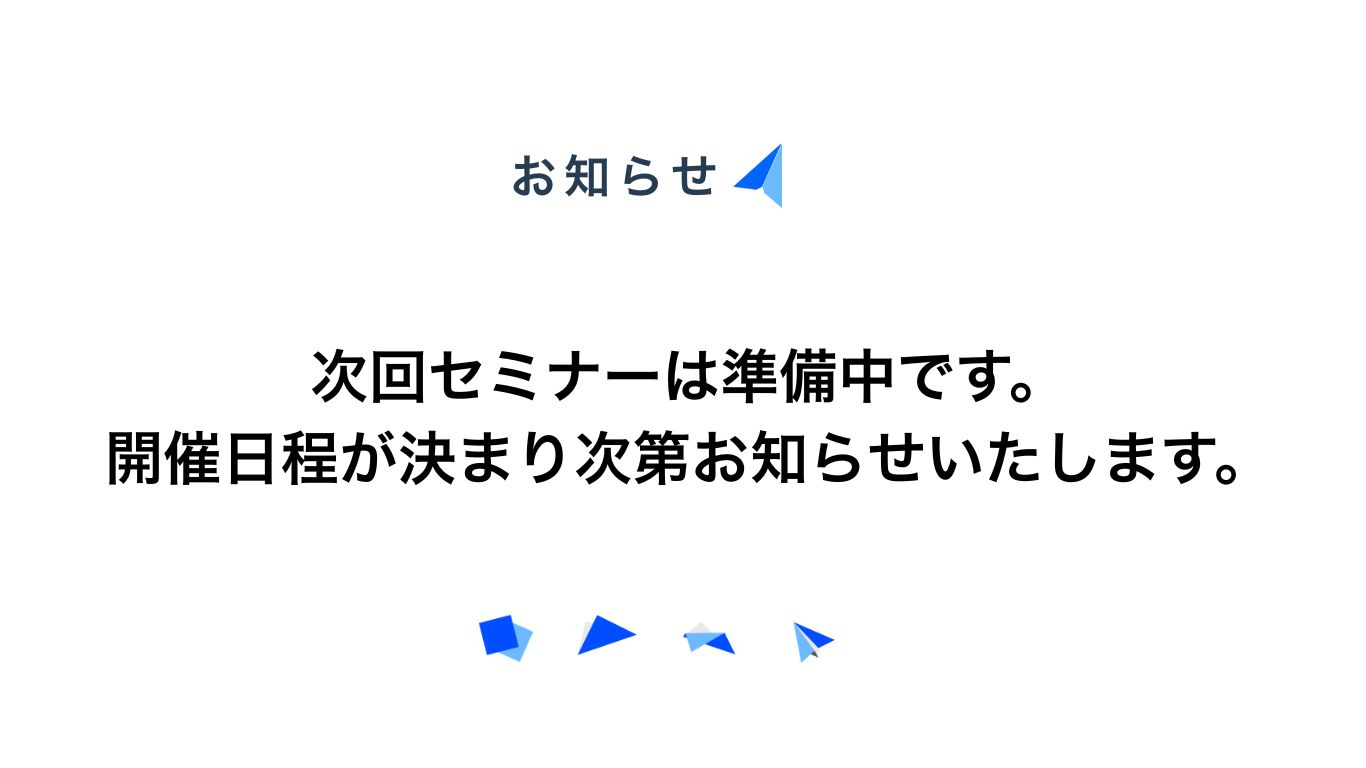―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は11月10日週に1.64円と、その前の週の1.67円から小幅縮小した。週足では反発。前週比では1.10円の上昇となり、年初来リターンは前週の2.5%安から1.8%安へ下げ幅を縮めた。高市首相の「デフレ脱却に至っていない」との発言や、12月利下げをめぐり米連邦公開市場委員会(FOMC)参加者の間で意見対立との報道を受けて、ドル円は一時、2月初め以来の155円乗せを達成。米ADP全国雇用者数の週次ベースの弱含みや米株安によるリスクオフでドル円が下がる場面もあったが、売りは限定的だった。
- 高市政権下、2025年度の補正予算は前年度を上回る14兆円となる見通しだ。補正予算を土台に打たれる経済対策は、所得税がかかり始める「年収の壁」の引き上げ、ガソリン・軽油の暫定税率の廃止などに伴う大型減税も含めれば、17兆円、財政投融資を含めると、20兆円を超える公算。高市政権の下で立ち上がった「日本成長戦略会議」のメンバーは、11月17日発表のQ3実質GDP成長率がマイナス予想となるなかで、日銀が利上げを行えば、補正予算を組み日本経済を押し上げようとする政府と整合性が取れないと主張し、日銀の利上げ難しくなっている。
- 10月の日銀金融政策決定会合、「主な意見」では、タカ派的な見方が優勢となり、12月利上げの選択肢を確保した。しかし、高市政権の下では、12月利上げのトリガーは円安加速と言わざるを得ない。もっとも、0.75%で利上げ打ち止めと判断されれば、円安基調が続くリスクにも留意すべきだろう。介入以外には、間もなく公表が予想される米財務省発表の為替報告書など、外圧による円安を是正する材料が見当たらなくなりそうだ。
- ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙のFedウォッチャーであるニック・ティミラオス記者によれば、FOMC参加者の間で、12月利下げをめぐり意見が対立しているという。秋以降、特に11月の発言を振り返ると、FOMC投票メンバー12名のうち、利下げに前向きな見解を示した参加者は5人程度で、FF先物市場での12月利下げ織り込み度も44.4%へ低下し、据え置き予想が過半数を占める。ただ、今後は今週11月20日の米9月雇用統計を始め、米経済指標が順次発表されるほか、ADPの週次データは雇用の減少を確認した。労働市場次第では12月利下げのシナリオは否定できない。一方で、トランプ政権は2,000ドルの関税「配当」を行う見通しで、物価高止まりの不確実性も横たわる。インフレ抑制と景気下支えの間で、Fed内のリスク・バランスをめぐる綱引きが続く。
- ドル円は非常に強い地合いにシフトした。日足では、2024年7月の高値と2025年1月の高値を結んだトレンドラインを上回って週を終えた。一目均衡表の三役好転を維持。週足でも、終値が前述のトレンドラインに着地しており、サプライズ要因にさえ見舞われなければ、上値を試す地合いにある。
- 11月17日週の経済指標は、17日にQ3実質GDP成長率・速報値、9月鉱工業生産、米11月NY連銀製造業景気指数、18日には米ADPの週次データ、米11月NAHB住宅市場指数、19日は日本9月機械受注、英10月CPI、20日は米9月雇用統計、米11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、米10月中古住宅販売件数、21日に日本10月全国CPI、英10月小売売上高、ユーロ圏、独、米の11月総合PMI・速報値、米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値が控える。
- その他、政府・中銀関連では、17日にウォラーFRB理事やウィリアムズNY連銀総裁、ミネアポリス連銀総裁の発言、18日に豪中銀議事要旨、リッチモンド連銀総裁とダラス連銀総裁の発言、19日に日本20年利付国債入札、10月分のFOMC議事要旨、NY連銀総裁とリッチモンド連銀総裁の発言、エヌビディアの決算、20日に中国最優遇貸出金利の発表、小枝日銀審議委員の発言、クリーブランド連銀総裁の他シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀総裁の発言、21日にラガルドECB総裁やNY連銀総裁、ダラス連銀総裁の発言を予定する。
- 以上を踏まえ、今週の上値の目途は心理的節目の 156円、安値は11月安値付近の152.80円と見込む。
1.ドル円振り返り=高市首相の「デフレ脱却に至らず」発言や12月利下げの不透明感で、ドル円は一時155円乗せ
【11月10日~7日のドル円レンジ:153.40~155.05円】
ドル円の変動幅は11月10日週に1.64円と、その前の週の1.67円から小幅縮小した。週足では反発。前週比では1.10円の上昇となり、年初来リターンは前週の2.5%安から1.8%安へ下げ幅を縮めた。高市首相の「デフレ脱却に至っていない」との発言や、12月利下げをめぐり米連邦公開市場委員会(FOMC)参加者の間で意見対立との報道を受けて、ドル円は一時、2月初め以来の155円乗せを達成。米ADP全国雇用者数の週次ベースの弱含みや米株安によるリスクオフでドル円が下がる場面もあったが、売りは限定的だった。
10日のドル円は、買い優勢。米上院で民主党8人の議員が、フィリバスター阻止に必要な60票確保に向け共和党に協力した結果、米政府機関の再開への期待が膨らみ、ドル円の上昇につながった。日銀の主な意見は12月利上げの可能性を残す内容だったものの、ドル円の影響は限定的。むしろ、中川審議委員の発言がタカ派的でなく買いを後押しし、一時154.25円まで本日高値をつけた。
11日のドル円は、買いの流れが継続。東京仲値を付けるタイミングで一時154.49円まで本日高値を更新した。一旦は緩む場面がみられたものの、高市首相が日本はデフレを脱却したとは言えないと発言したため、日銀の利上げは困難との見方を下支えし、154円台を維持。NY時間に発表された米ADPの週次速報値で10月後半の雇用削減を確認し、一時153.67円まで本日安値をつけたが、下値は拾われ154円台へ戻してNY時間を終えた。
12日、ドル円は続伸。引き続き買いが優勢となり、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙のFedウォッチャーであるニック・ティミラオス記者が12月FOMCの利下げを巡り判断が分かれていると報じたこともあって、154.50円を超え154.70円台へ上昇した。片山財務相が円安をめぐり、「マイナス面が目立ってきていることは否定できない」と発言したが、154円半ばへゆるむ程度に。むしろ、高市首相が改めて、インフレは食品価格によるものでデフレ脱却に至っていないと発言したため、上方向のトレンドは変わらず。経済財政諮問会議で植田総裁と初顔合わせした際に、「強い経済成長と安定的な物価上昇の両立に向け、適切な金融政策運営が行われることが重要だ」と報じられたことも、買い材料となった。NY時間には特に材料が出ないなかで2月初め以来の155円を突破し、一時155.05円まで週の高値を更新した。
13日、ドル円は買い基調を維持。10月企業物価指数が前月以下にとどまり、ドル円は一時155.02円まで本日高値を更新した。もっとも、その後は上値が重い展開。植田総裁が、現状の物価高の要因がデマンドプル型かコストプッシュ型か問われ「明確に識別することは、なかなか難しい」と発言したと報じられ、買い戻しが入るも155円に届かず。NY時間には米株安を受けて一時154.13円まで本日安値を更新したが、下値も限定的だった。
14日、ドル円は小幅安。東京時間の序盤にWSJ紙のニック・ティミラオス記者によるバーFRB理事とミネアポリス連銀総裁の12月利下げに否定的なコメントに関するXの投稿を受け、ドル円は底堅く推移した。一時154.76円まで本日高値を更新。ロンドン時間に入ると、リーブス英財務相が所得増税方針を転換する見通しとの報道を受け、英国債利回りが急伸するに合わせ、ポンドが急落した。一方で、ユーロポンドの上昇もあって、ユーロ円は一時179.98円と前日に続き最高値を更新。クロス円の上昇に支えられたが、NY時間には米株安と米債利回り低下に合わせ、ドル円は154円を割り込み、一時153.62円まで本日安値をつけた。もっとも、10日につけた週安値153.40円に届かず、米株の下げ幅縮小もあって154円半ばへ切り返して週を終えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!