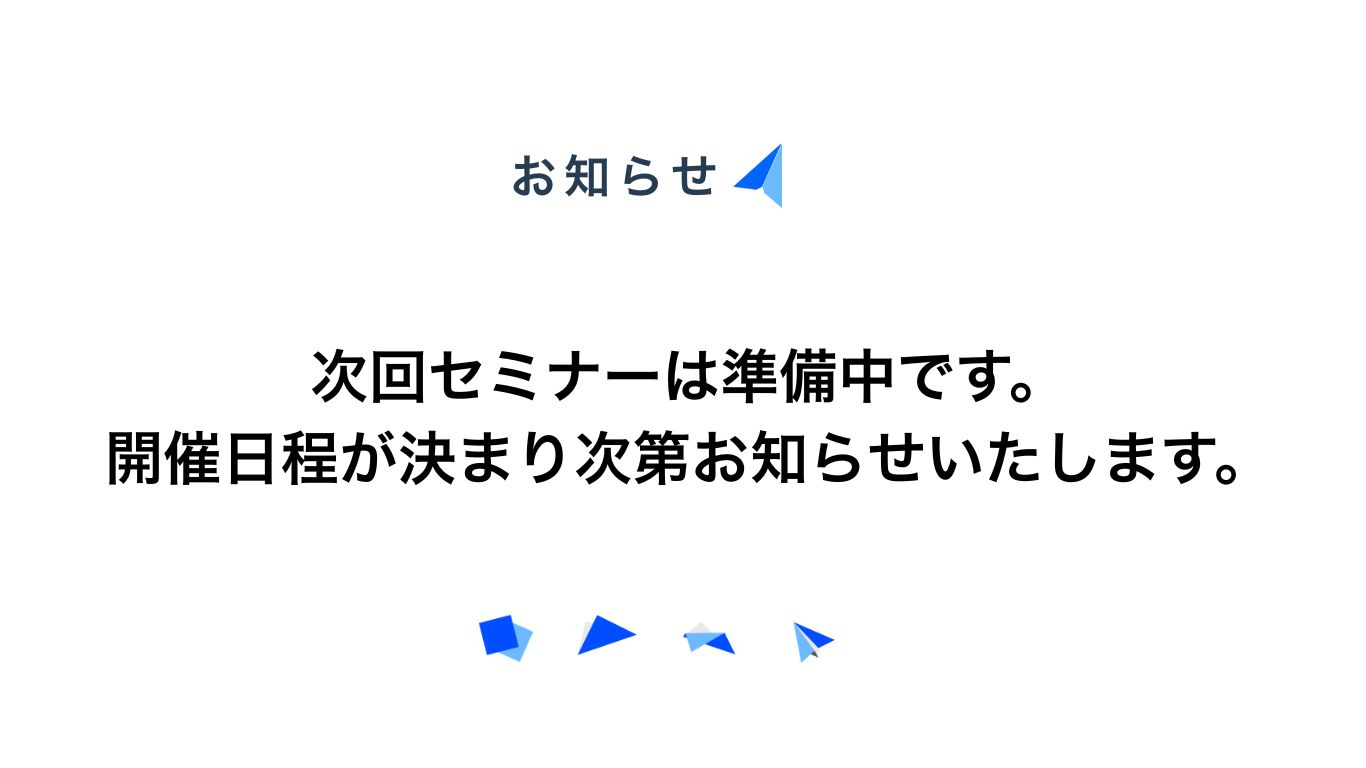―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は11月17日週に3.52円と、その前の週の1.64円から大幅拡大した。週足では続伸。前週比では1.80円の上昇となり、年初来リターンは前週の1.8%安から0.6%安となったが、一時はプラスに転じる場面がみられた。高市政権の日本成長戦略本部のメンバーが12月と2026年1月の利上げ観測を否定したほか、片山財務相が自身と城内経財相、植田総裁との三者会談後に「為替について具体的な話は出なかった」と発言したため、ドル円は一気に1月半ば以来の158円乗せを視野に入れた。米9月雇用統計・非農業部門就労者数(NFP)が市場予想を上回ったことも、ドル円を押し上げ。ただ、米株安に加え、片山財務相の発言による介入警戒感が高まり、NY連銀総裁が利下げ余地示したことも重なって、ドル円は156円前半で週を終えた。
- 12月利下げをめぐり、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙のFed番記者であるニック・ティミラオス記者が、米連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーの間で意見が対立していると報じ、FF先物市場での利下げ織り込み度は一時20.4%台まで低下した。ところが、NY連銀総裁が11月21日に、短期的に利下げ余地ありと発言し、一転して利下げ織り込み度は70%超えへ巻き返した。背景には、米労働市場の軟化に加え、金融市場の資金ひっ迫を緩和する意図がありそうだ。特に、AI投資はプライベート・クレジット(銀行以外の民間貸し手が、企業など借り手に対して直接行う融資)の関与が取り沙汰されるが、米商業銀行のプライベート・クレジットを含むノンバンク系金融機関(NDFI)の融資額は1.7兆ドルを超え、そのプライベート・エクイティ合わせ約半分を占めるだけに、引き締め的な政策の調整が必要と認識しているのではないか。
- 片山財務相が11月21日、ドル円が年初来高値に迫るなか為替介入について「当然考えられる」、「いざとなったら断固たる措置も辞さず」と発言した。高市政権下で発足した日本成長戦略会議のメンバーも、積極的な介入に言及しており、日銀の利上げの前に介入の可能性が見えてきた。もっとも、日銀の利上げの前に介入に踏み切るならば、日米財務相共同声明で「過度な変動」も場合などに制限されているだけに、米国との意思疎通が必要となりそうだ。一方で、植田総裁が円安の物価への影響が大きくなる可能性に言及し、小枝審議委員や増審議委員からも利上げに前向きな発言を確認しており、引き続き12月利上げのカードも温存されていると言えよう。
- ドル円は非常に強い地合いにシフトした。日足では、2024年7月の高値と2025年1月の高値を結んだトレンドラインから上放れするだけでなく、週足でつけたダブルトップのネックライン(158.88円)を伺いつつある。何より、前述したように、①年初来リターンが一時的にプラスに反転、②プラザ合意前の長期トレンドラインの半値戻しを一時的に達成、③ユーロ円やCHF円で過去最高値を更新、豪ドル円やポンド円など他のクロス円では年初来高値を更新するなど、クロス円を通じた上昇圧力――などを受け、上値トライの勢いを感じさせる。ただし、今週は米国の感謝祭を控え、動意薄となりそうだ。また、片山財務相の発言もあって、介入警戒が強まっており、利益確定の売りが出るシナリオも考えられよう。
- 11月24日週の経済指標は、24日に独11月Ifo企業景況感指数、25日に米9月小売売上高と米9月生産者物価指数、米11月消費者信頼感指数、26日に日本10月企業向けサービス価格指数、豪10月CPI、米新規失業保険申請件数、米9月耐久財受注、米11月シカゴ購買部協会景気指数を予定する。28日は日本10月失業率と有効求人倍率、日本11月東京都区部CPI、独11月CPI速報値などが控える。
- その他、政府・中銀関連では、24日にラガルドECB総裁、26日にニュージーランド準備銀行(RBNZ)の政策金利発表、米地区連銀経済報告(ベージュブック)の発表、27日にECB理事会議事要旨の発表を予定する。
- 以上を踏まえ、今週の上値の目途は心理的節目の 158.00円、安値は21日移動平均線が近い154.50円と見込む。
1.ドル円振り返り=高市政権の補正予算や日銀利上げ観測後退を受け、1月半ば以来の158円乗せが視野に
【11月17日~21日のドル円レンジ:154.37~157.90円】
ドル円の変動幅は11月17日週に3.52円と、その前の週の1.64円から大幅拡大した。週足では続伸。前週比では1.80円の上昇となり、年初来リターンは前週の1.8%安から0.6%安となったが、一時はプラスに転じる場面がみられた。高市政権の日本成長戦略本部のメンバーが12月と2026年1月の利上げ観測を否定したほか、片山財務相が自身と城内経財相、植田総裁との三者会談後に「為替について具体的な話は出なかった」と発言したため、ドル円は一気に1月半ば以来の158円乗せを視野に入れた。米9月雇用統計・非農業部門就労者数(NFP)が市場予想を上回ったことも、ドル円を押し上げ。ただ、米株安に加え、片山財務相の発言による介入警戒感が高まり、NY連銀総裁が利下げ余地示したことも重なって、ドル円は156円前半で週を終えた。
17日のドル円は、上値を試す展開。日本Q3実質GDP成長率が予想より悪化せず、ドル円は下落したものの154.42円まで週の安値を付けるにとどまり、以降は前週末に高市政権の補正予算が財投融資を含め20兆円となる見通しと報道されたこともあって、日本株安でも買いが優勢となった。日本成長戦略会議メンバーに就任した片岡剛士・PwCコンサルティング上席執行役員・チーフエコノミストが、マイナス成長を受け12月利上げなし、26年1月もインセンティブなしと発言したことも、材料視。NY時間には、米株が下落してスタートした後、プラスに転じる場面に合わせ155円台を回復した。ジェファーソンFRB副議長が中立金利に近づく中で利下げに慎重となるべきとの見解を寄せると、一時155.31円まで本日高値を更新。大台を保ってNY引けを迎えた。
18日のドル円は、続伸。片山財務相が「非常に一方的な、また急激な動きもみられて憂慮している」との認識を示した。さらに「為替市場における過度な変動や無秩序な動きについては高い緊張感を持って見極めているところだ」と発言したが、反応は限定的で155円前半の推移を続けた。東京時間の昼過ぎに日本株安を受けて一時154.82円まで本日安値を更新も、大台割れでは押し目を拾われる展開。高市首相と植田総裁の会談では、植田氏いわく首相からは政策面の要請や要望はなかったとされ、再び155円割れもすかさず買いが入った。NY時間は再び買いが優勢となり、155円台へ戻し一時155.74円と2月初め以来の高値を更新した。
19日、ドル円は大幅高。片山財務相、城内経財相、植田総裁の三者会談を前に、ドル円は一時155.22円まで本日安値を更新した。政府の日本成長戦略会議のメンバーで元日本銀行審議委員の片岡氏が補正予算の効果で内需が高まる見通しの2026年3月に利上げの環境が整うと述べたが、ドル円への影響は限定的だった。しかし、三者会談後、片山氏が「為替について具体的な話は出なかった」と発言した結果、足元の水準を容認したとの思惑が強まり、右肩上がりの展開。156円を軽々と突破しただけでなく、NY時間には米労働統計局が米10月雇用統計を発表せず、米11月雇用統計は12月FOMC明けに発表すると明かしたため、一段高を迎えた。注目された半導体大手エヌビディアの好決算も重なり、1月半ば以来の157円も抜け、一時157.19円まで上値を広げた。
20日、ドル円は買い基調を維持。前日の現地時間の引け後に発表されたエヌビディア決算を受け日本株が大幅高を迎えた流れを受け、ドル円は東京時間から買いが優勢となった。小枝日銀審議委員がタカ派的な見解を寄せたものの、市場はスルー。木原官房長官が口先介入を行ったものの、片山財務相が「物価・金利・円安のすべてのバランスを取ることは大変難しい」と、円一段安の阻止が困難と言った含みを持たせる発言を行い、ドル円の上昇に流れは止まらず。NY時間には、米9月雇用統計・NFPが市場予想を上回ったことも重なり、一時157.90円と1月半ば以来の158円乗せが視野に入った。ただ、エヌビディアの好決算後ながら、AIバブルへの警戒感が払しょくされず、米株がマイナスに転じ、上げ幅を縮小した。
21日、ドル円の上昇が一服。東京時間は、前日の米株安に加え、日本成長戦略会議のメンバーであるクレディ・アグリコルの会田卓司チーフエコノミストが、160円に達する前に為替介入がありうるとの見解を示し、ドル円は軟調に推移した。高市首相が「補正後の国債発行額は昨年度の42.1兆円を下回る見込み」と発言したが、なかなか157円を割り込まず。しかし、片山財務相が、為替介入について「当然考えられる」、「いざとなったら断固たる措置も辞さず」と発言、植田総裁が衆院財務金融委員会で、円安の物価への影響が大きくなる可能性に言及するなか、ロンドン時間に入りようやく157円を割り込んだ。NY時間に入ると、NY連銀総裁が短期的に利下げ余地ありと発言したほか、増審議委員が利上げが近いと発言、ドル円は下値を広げ一時156.20円まで本日安値を更新した。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!