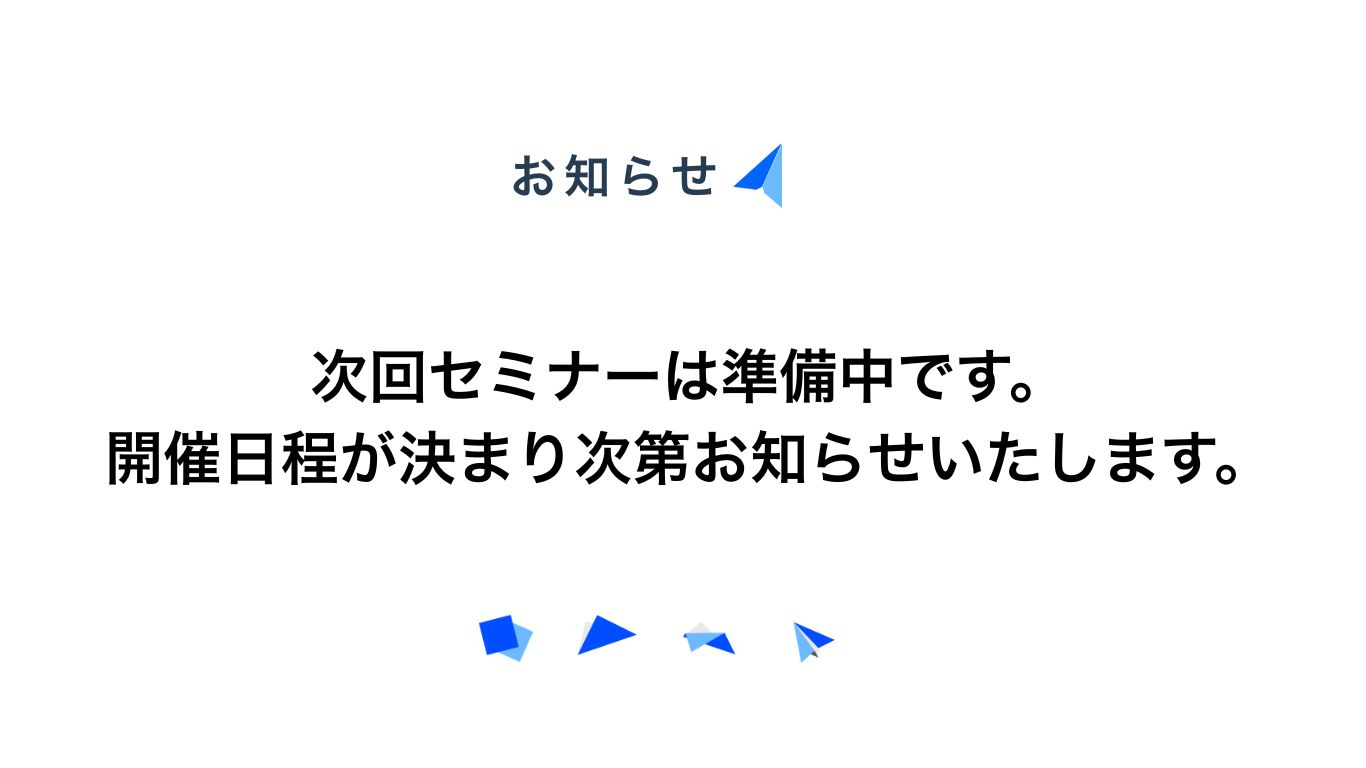―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は5月19日週に3.09円と、その前の週の3.73円から縮小した。週足では、5週ぶりに反落。前週比では3.08円の下落となった。年初来リターンは9.4%安へ拡大した。G7財務相・中央銀行総裁会議や3回目の日米財務相会談を控え、為替をめぐる協議が意識された。結局、G7会合でも日米財務相会談でも目新しい材料は確認できなかったものの、ドル円の下落の流れは変わらず。週末にトランプ大統領が交渉難航を理由に欧州連合(EU)に対し関税を50%へ引き上げる可能性に言及したため、不確実性が高まり売り下値を広げた。
- トランプ大統領は5月23日、通商協議が難航する欧州連合(EU)に対し、50%の関税を課す可能性を表明した。シェフチョビッチEU通商担当委員がラトニック米商務長官とジェミソン・グリア米通商代表部代表との電話会談を行う数時間前に、警告した格好だ。米国の対EU貿易赤字(財)は2024年に2,356億ドルと、中国の2,954億ドルに次ぐ規模で、トランプ政権が貿易赤字を是正する上では重要な相手である。加えて、EUはトランプ政権が4月2日に相互関税を発表してから、報復関税を発表してきた数少ない国・地域のひとつ。トランプ政権にしてみれば、ベッセント財務長官が言うところの「真摯な姿勢」でない例外の地域として、圧力を掛ける必要があったと考えられる。5月25日には、フォンデアライエン欧州委員長との電話会談を経て、トランプ大統領は50%関税適用を7月9日に延期したと発表。過度な楽観と共に悲観も禁物ではないだろうか。
- G7財務相・中央銀行総裁会議が5月20ー22日に開催されたが、共同声明では関税に言及されず、むしろ「非市場的政策及び慣行(NMPPs)がどのように不均衡を悪化させ、過剰生産能力を助長し、他国の経済安全保障に影響を及ぼすかについて、共通理解の必要性を認識」との文言を盛り込んだ。一連の文言は、名指しこそ控えられたが、粗鋼生産を始め中国の過剰生産を念頭に入れたものと考えられ、ベッセント財務長官率いる米国の勝利と言えよう。各国にとっては、米国との通商協議を続けるなか協議の円滑化を狙ったものとも考えられる。
- 日米財務相会談後に発表された声明では、引き続き為替レートの水準について協議せずと明記された。これは、韓国経済新聞が韓国と米国が先月、関税撤廃を目指した協定を作成することで合意したと報じた内容と、対照的だ。日本との間で為替レートについて本当に協議されなかったかは定かではないが、日米財務相会談でドル高・円安是正について明確に協議されたと判明すれば、無秩序なドル安に陥りかねず、かつ日銀の金融政策正常化も遅らせかねない。日米間では、こうした点に配慮した可能性がある。
- 赤沢経済再生相は来週にも、4回目の日米協議に向け訪米すると発言した。これに合わせ、トランプ大統領は5月23日、日本製鉄とUSスチールの「提携」について発表。日鉄による141億ドル(約2兆円)の買収案が受け入れられたかは不透明だが、石破首相は6月のG7首脳会議に合わせ、訪米を含めトランプ大統領との首脳会談を行う方向性に言及。トランプ大統領が「USスチールは米国がコントロール」と発言するなか、日米首脳会談に合わせ、通商協議が進展すると共に、日鉄とUSスチールの「提携」についても明らかになるのはないか。なお、日鉄とUSスチールの提携が買収とされ、141億ドルが米国で投資されるなら、ドル高・円安材料で、為替市場に影響を与えそうだ。ただし、日本生命による約1.2兆円規模の米生保買収劇を踏まえれば、影響が一時的となってもおかしくない。また、ベッセント財務長官が言及した補完的レバレッジ比率(SLR)の条件緩和も、米金利低下=ドル安につながるため、留意すべきだ。
- 5月26日週に発表となる主な経済指標として、27日に日本4月期企業向けサービス価格指数、米4月耐久財受注、米5月消費者信頼感指数、米2年債入札、28日に豪4月消費者物価指数、独5月失業率、米5年債入札、29日に米Q1実質GDP改定値、米新規失業保険申請件数、米7年債入札、30日に日本4月失業率や有効求人倍率、日本5月東京都区部CPI、米4月PCE価格指数、米5月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値を予定する。
- その他、政治・中銀関連では26日にラガルドECB総裁の発言、東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議、27日には日銀国際カンファレンスを受け植田総裁や、NY連銀総裁、ミネアポリス連銀総裁の発言、東南アジア首脳会議とサウジアラビアなどが加盟する湾岸協力会議(GCC)との合同会議、28日に日銀国際カンファレンスでのミネアポリス連銀総裁の発言、日本の40年債入札、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)の政策金利発表、5月FOMC議事要旨、29日にリッチモンド連銀総裁を始めシカゴ連銀総裁、クーグラーFRB理事、サンフランシスコ連銀総裁、ダラス連銀総裁の発言、30日にサンフランシスコ連銀総裁の発言を予定する。30日には赤沢再生相が再び米国訪問し、ベッセント財務長官などと第4回目の日米協議を行う見通しである他、アジア安全保障会議がシンガポールにて6月1日まで開催される。
- ドル円のテクニカルは、弱含みが継続。ドル円は5月7ー8日に開催されたFOMC後の上げ幅を打ち消し、5月6日の安値142.35円に接近中だ。また、21日移動平均線があらためて抵抗線として意識される。ドル円の下方向のトレンドが継続すれば、再び140円割れを試す展開もあり得よう。RSIは14日移動平均線を下抜けデッドクロスが形成されたことも、ドル円にはネガティブ材料だ。
- 以上を踏まえ、今週の上値は50日移動平均線と一目均衡表の転換線が近い145.50円、下値は4月22日の安値が近い139.80円と見込む。
1.先週のドル円振り返り=トランプ大統領がEUに関税50%を警告、ドル円を押し下げ
【5月19~23日のドル円レンジ: 142.42~145.51円】
ドル円の変動幅は5月19日週に1.68円と、その前の週の3.73円から縮小した。週足では、5週ぶりに反落。前週比では3.08円の下落となった。年初来リターンは9.4%安へ拡大した。G7財務相・中央銀行総裁会議や3回目の日米財務相会談を控え、為替をめぐる協議が意識された。結局、G7会合でも日米財務相会談でも目新しい材料は確認できなかったものの、ドル円の下落の流れは変わらず。週末にトランプ大統領が交渉難航を理由に欧州連合(EU)に対し関税を50%へ引き上げる可能性に言及したため、不確実性が高まり売り下値を広げた。
19日、ドル円は軟調。前週末に米大手格付け会社ムーディーズが米国債の格付けを引き下げたため、リスクオフの流れからドル売りが優勢となった。時間外で米債も売られ米10年債利回りが上昇したことも意識。ドル円はロンドン時間入りに一時144.66円まで本日安値を更新したが、NY時間では下げ渋った。
20日、ドル円は東京序盤に買われたが前日からの売りの流れが継続。東京仲根の時間帯に一時145.51円まで本日高値を付けたが、加藤財務相がG7財務相・中央銀行総裁会議の日程に合わせ行われる予定のベッセント米財務長官との協議について、為替など諸課題を議論と発言したため、145円を割り込んだ。東京時間の昼頃にベッセント財務長官が今週末予定の赤沢再生相との関税に関する協議に出席しないとの報道が出ると、日米通商協議で為替について議論されないのではとの観測からドル買い・円売りで反応も、一時的。豪準備銀行(RBA)が市場予想通り利下げを行ったほか、声明文がハト派寄りで豪ドル円が下落すると、ドル円の連れ安となった。また、日本の20年債入札が不調に終わると、リスクオフの展開からドル円は売りが優勢となり、一時144.09円まで本日安値を更新した。NY時間では、前日に続き下げ渋った。
21日、ドル円は売り優勢。G7財務相・中央銀行総裁会議の開催を受け、加藤財務相とベッセント米財務長官の会談が意識されるなか、ドル円は売りの流れが続いた。イスラエルがイラン核施設への攻撃を準備しているとの報道も、リスク回避の動きからドル売り・円買いにつながった。ロンドン時間には144円半ば付近へ買い戻される場面もあったが一時的で、NY時間入りには、「米国が通貨高に向けた対策を求めた」、「韓国と米国は先月、関税撤廃を目指した協定を作成することで合意。ベッセント米財務長官の要請で通貨政策でも個別に協議」との報道を受けて、ドル円は押し下げられ、NY時間には米20年債入札が不調だったため、一時143.28円まで本日安値を更新した。
22日、ドル円は乱高下。G20財務相・中央銀行総裁会議を経て、加藤財務相とベッセント財務長官が日米財務相会談を行い、声明では「為替は市場で決定されるべき」など従来の文言が明記された程度で、ドル円は急伸、一時144.42円まで本日高値を更新した。しかし、買いの流れは続かずいって来いの展開。ロンドン時間には、ユーロ圏や独のPMI速報値が弱く、ユーロ円でのユーロ売り円買いが出たため、ドル円の重石となり、一時142.80円まで本日安値を更新した。NY時間には、トランプ大統領肝入りの大型減税法案が下院で可決し買い戻されたが、144円前半までにとどまった。
23日、ドル円は売りが再燃。4月全国消費者物価指数(CPI)のコアなどがインフレ加速を示し、ドル円は軟調にスタートした。ロンドン時間では143円前半でもみ合いとなったが、NY時間入りにトランプ大統領がEUに交渉難航を理由に関税を50%引き上げる可能性に言及したほか、米国以外で生産されたiPhoneに対し、アップルに関税を発動すると警告したため、不確実性が高まりドル円は143円前半から急落。一時142.42円と5月6日以来の安値をつけ、そのまま安値圏で取引を終えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!